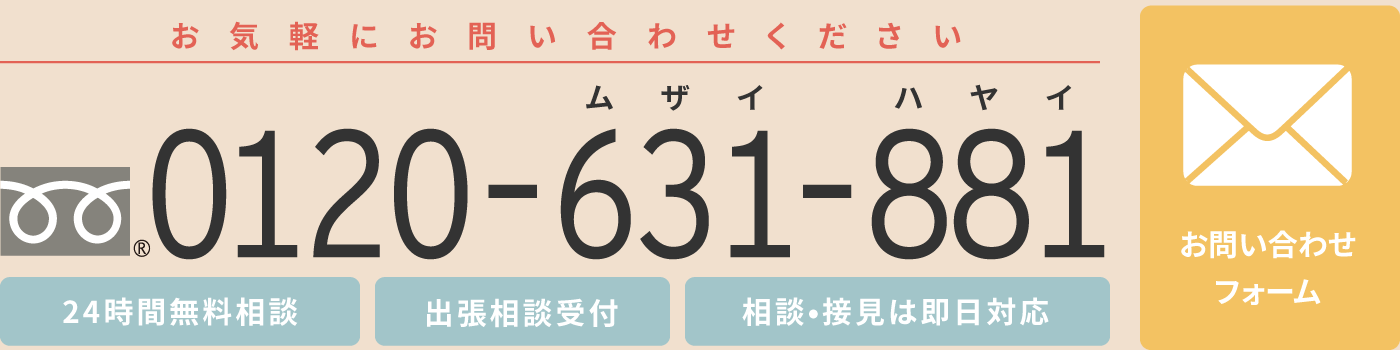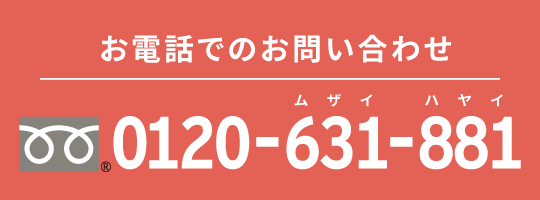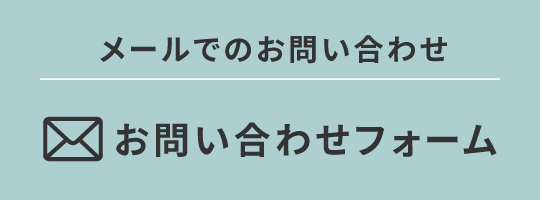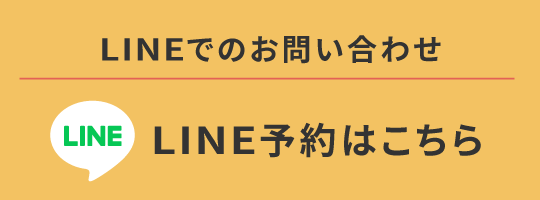公金官物は公共の利益のために使われるものです。公務員がこれを損ねることは、大きな非難に値し、厳しい懲戒処分が下されます。
ここでは、公務員の公金官物取り扱いについて解説します。
公金官物の取り扱いに関する犯罪
窃盗
他人の財物を窃取した者は、10年以下の懲役又は10年以下の拘禁刑に処されます(刑法第235条)。
他の職員の持ち物や現金を持ち去る場合が典型的です。
また、後述の業務上横領のように見える行為でも、自身の「占有」がない現金などを持ち去れば、この窃盗罪が成立します。
詐欺
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の拘禁刑に処されます(刑法第246条第1項)。
要件を満たしていないのに、用件を備えているかのように誤信させて、手当てを受給することは、この詐欺罪に該当すると考えられます。
業務上横領
自己の占有する他人の物を横領した場合横領罪(単純横領罪)が成立し、5年以下の拘禁刑に処されます(刑法第252条第1項)。これが業務上自己の占有する他人の物の場合、業務上横領罪は10年以下の拘禁刑(刑法第253条)に処されます。
「占有」とは、事実上の占有だけでなく、法律上の占有も含まれます。預金なども対象になり得ますが、預金通帳やキャッシュカード等を事務的に預かっているだけでは預金を占有しているとはいえません。
「業務」とは、人がその社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務です。公務員がその仕事として行うものであれば「業務上」占有すると判断されるでしょうから、公務員がその業務に関係する物を横領した場合は、多くは業務上横領罪に当たるでしょう。
「横領」とは、不法領得の意思を実現する一切の行為をいいます。この「不法領得の意思」とは、「他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思」をいうとされています。金銭の着服は横領の典型的な行為です。
警察官舎の管理人が積立金を着服するようなことをすれば、業務上横領に該当するでしょう。着服の他に「横領」に該当する行為の態様は、毀棄・隠匿のほか、売却や貸与、譲渡担保や抵当権などの担保権の設定、質入れなど多彩な行為が考えられます。
官物損壊
公務所の用に供する文書又は電磁的記録を棄損すると、公用文書等毀棄罪が成立し、3月以上7年以下の拘禁刑に処されます(刑法第258条)。
それ以外の物を損壊すると、器物損壊罪が成立し、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金若しくは科料に処されます(刑法第261条)。
懲戒処分
公務員の公金官物取り扱いを誤ると、犯罪に該当するほか、非違行為をしたとして、懲戒処分を受けます。
自衛官などの国家公務員については、人事院の定める「懲戒処分の指針について」に基づいて懲戒処分が下されます。
「懲戒処分の指針」の「第2 標準例」に「2 公金官物取扱い関係」が定められています。横領や窃取、詐取は免職となります。故意の犯罪による場合だけでなく、過失による場合も処分を受けることがあります。
2 公金官物取扱い関係
(1) 横領
公金又は官物を横領した職員は、免職とする。
(2) 窃取
公金又は官物を窃取した職員は、免職とする。
(3) 詐取
人を欺いて公金又は官物を交付させた職員は、免職とする。
(4) 紛失
公金又は官物を紛失した職員は、戒告とする。
(5) 盗難
重大な過失により公金又は官物の盗難に遭った職員は、戒告とする。
(6) 官物損壊
故意に職場において官物を損壊した職員は、減給又は戒告とする。
(7) 失火
過失により職場において官物の出火を引き起こした職員は、戒告とする。
(8) 諸給与の違法支払・不適正受給
故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員は、減給又は戒告とする。
(9) 公金官物処理不適正
自己保管中の公金の流用等公金又は官物の不適正な処理をした職員は、減給又は戒告とする。
(10) コンピュータの不適正使用
職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。
まとめ
このように、不適切な公金官物の取り扱いをした公務員は、非常に重い処分を下されることになります。
公金官物の取り扱いについてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
こちらの記事もご覧ください