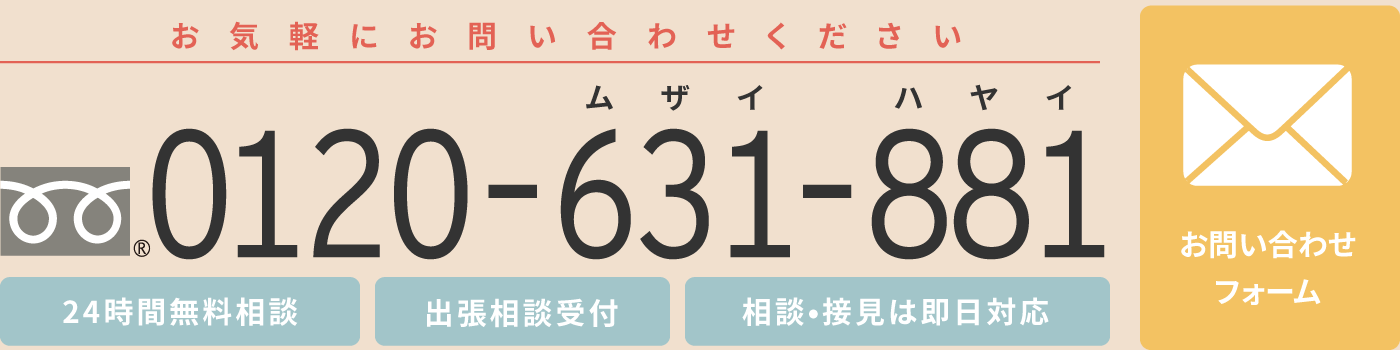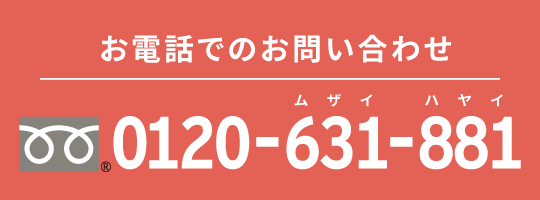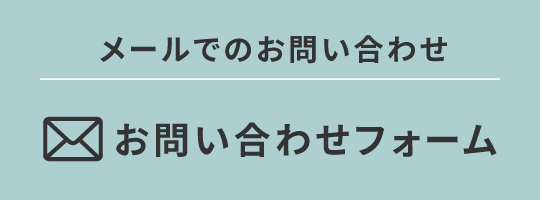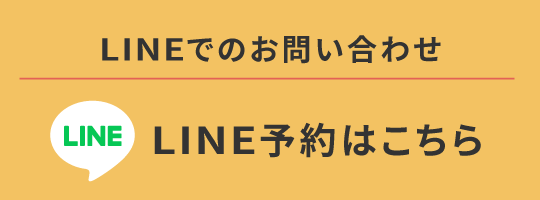【事例(フィクション)】
公立学校で教員として勤務するAさんは、飲酒をした後に自動車を運転してしまい、その後職務質問で警察から呼気検査を求められ、検査の結果、呼気中に基準値を超えるアルコールが検知され、酒気帯び運転で検挙されました。
Aさんは逮捕はされませんでしたが、在宅捜査中です。
Aさんは、酒気帯び状態で自動車の運転をしたことは認めています。
Aさんに前科前歴はありません。
【被疑者の方が公立学校教員の場合のリスク】
公立学校に勤務する教員は、地方公務員となります。
公立学校教員の方が刑事事件の被疑者となった場合、刑事手続き上の逮捕・勾留や刑事罰のリスクだけでなく、地方公務員法上の懲戒処分や、失職等のリスクにもさらされることとなってしまいます。
以下、弁護活動も含め、順に説明していきます。
【飲酒運転の刑事罰】
アルコール濃度が血液1mlにつき0.3mg又は呼気1リットルにつき0.15mg以上の状態で自動車を運転すると、酒気帯び運転として、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます(道路交通法117条の2の2第1項第3号・道路交通法施行令44条の3)。
酒気帯び運転の場合、初犯は罰金となることが多いですが、身体のアルコール濃度、運転した理由、距離等の事情次第で悪質と判断されれば、初犯でも公判請求され、執行猶予が付く可能性が高いとはいえ懲役の前科がつくこともあり得ます。
なお、身体のアルコール濃度を問わず、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転すると、酒酔い運転として、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金というより重い刑に処されます(道路交通法117条の2第1項第1号)。
【弁護活動】
①今後のAさんの刑事処分が決まるにあたって、取調べ対応は重要です。できるだけ弁護士が取調べの初期からついて、継続的にアドバイスができるようにするのが望ましいです。
②検察官が起訴するかどうか、起訴の場合は略式起訴か公判請求かを決める前に、弁護士から、酌むべき事情を主張する意見書を提出し、刑事処分の軽減を図ることも考えられます。
③もしAさんが公判請求された場合は、弁護士が酌むべき事情を主張立証し、執行猶予が付いて実刑は回避できるように、また事情次第では懲役より軽い罰金となることを裁判所に求めるなどして、処罰軽減のため公判活動をすることになります。
【刑事罰以外の処分等】
地方公務員の方は、起訴されると、休職をさせられることがあります(地方公務員法28条2項2号)。
そして起訴され、有罪判決で禁錮以上の刑となれば、執行猶予が付いたとしても、失職することになります(地方公務員法28条4項・16条1号)。
事例の場合、Aさんに前科前歴はなく、一般的には罰金の可能性が高いので、そうなればこの規定による失職はありません。
しかし、上で述べたとおり、事情次第では初犯でも公判請求されて執行猶予付き懲役刑となることはあり得るので、油断はできません。
また、地方公務員の方が犯罪にあたる行為をすると、刑事罰とは別に懲戒処分を受けることにもなります。
懲戒処分は、重い順に、免職、停職、減給、戒告と種類があります。
東京都教育委員会が公表している「懲戒処分の指針」によると
「具体的な量定の決定に当たっては、
① 非違行為の態様、被害の大きさ及び司法の動向など社会的重大性の程度
② 非違行為を行った職員の職責、過失の大きさ及び職務への影響など信用失墜の度合い
③ 日常の勤務態度及び常習性など非違行為を行った職員固有の事情等のほか、適宜、非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものとする。
個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる量定にかかわらず免職等の処分をすることもあり得る。」
としつつ、標準例では「酒気帯び運転をした職員は、免職又は停職とする。」とされています。
Aさんの場合、免職又は停職のリスクがあることとなりますが、上の指針からわかるとおり懲戒処分の選択は総合判断なので、あきらめずに処分軽減の余地があるか、弁護士に相談することをおすすめします。
【おわりに】
酒気帯び運転をしてしまった公立学校教員の方は、刑事罰、失職、懲戒処分等のリスクにさらされますが、こういったリスクを回避・軽減するためには、弁護士による適切なアドバイスや活動が必要ですので、できるだけ早めに弁護士に相談することをおすすめします。
こちらの記事もご覧ください