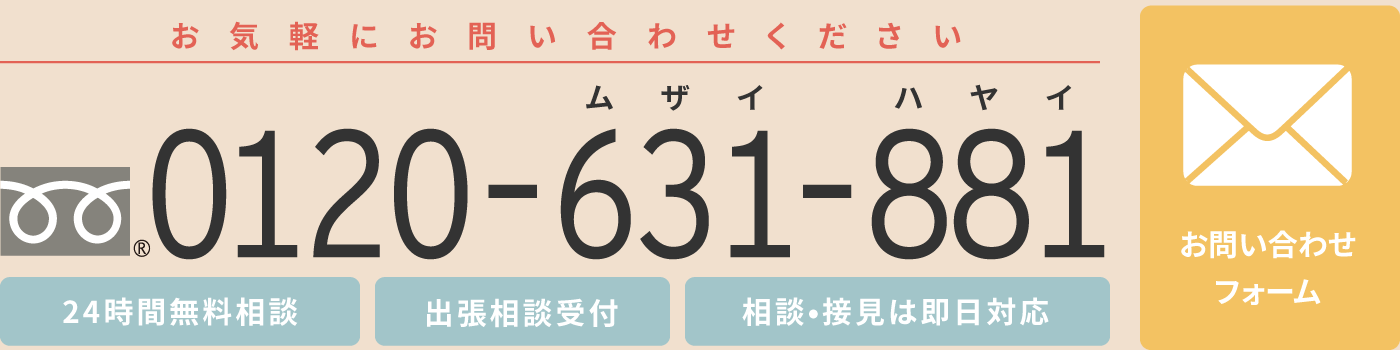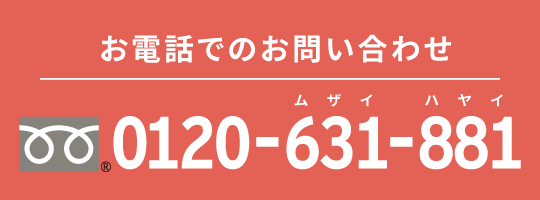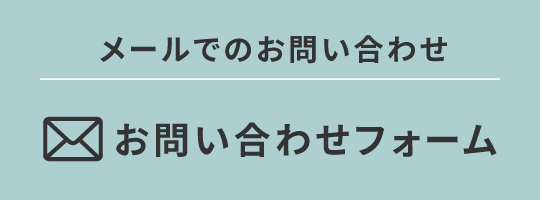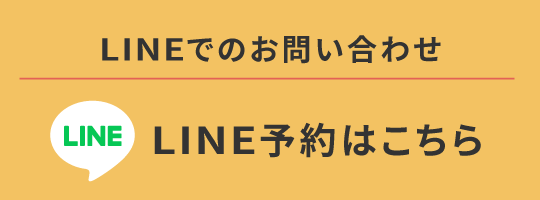Archive for the ‘懲戒処分等’ Category
公務員の懲戒 部下からのパワハラ
公務員の懲戒 部下からのパワハラ

公務員の方であれば、犯罪行為をした場合はもちろんのこと、犯罪行為に当たらなくても、パワハラ、セクハラなどの職場内秩序を乱す行為が懲戒処分に繋がっていくことを御存知かと思います。
今回は、その部下から上司にされたパワハラとして紹介・減給されている事例について検討します。
実際の事例
https://news.yahoo.co.jp/articles/bb35989c08bb1867f6117c0b6f88bcc6b353fc5b
(Yahoo!ニュース。令和7年8月26日閲覧。)
相模原市教育委員会は21日、市立小学校の男性教諭(23)を減給1カ月(給与月額の10分の1)の懲戒処分とした。
市教委によると、教諭は5月15日に小学3年生の学級トラブルの対応を巡り、教室内で児童が泣くほどの大きな声で男性校長(61)を怒鳴った。また、6月3日に「先生が来週から休むのはいじめられたことが原因。いじめた先生の話は聞かないように。この話は誰にも話さないように」と話し、1カ月間の傷病休暇を取得した。
教諭は4月10日、教職員が集まる場で校長の発言中に笑ったような表情をしたと、他の教諭から指摘されたことをいじめと捉え、繰り返し職場の秩序を乱すようになったという。
関係法令
上記の行為に関して、暴力や名誉棄損などは見当たりませんし、上司と部下の権力差を利用して行われた行為ではないと言えます。インターネットなどでは、部下が上司に対して児童生徒の前で怒るなどしていることから、逆パワハラ等と言われることがあります(https://news.yahoo.co.jp/articles/7516751524ae730c5a26d8cb0e07a7d1d7c0ba89 令和7年8月26日閲覧)。
ただし、校長に対して児童が無く程の大声で怒鳴る以外にも、いじめられたと主張して傷病休暇を取る、児童生徒に対して、「自分がいじめられた」と話す等、背景が全てわかるわけではありませんが、その他にも不適切な言動が目立っていた可能性もあります。
懲戒基準
相模原市の教職員懲戒基準は以下の通りです。
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/12/25/1412016_13.pdf
(令和7年8月26日閲覧)
上司等に対する暴言により職場の秩序を乱した教職員は、減給又は戒告とする。
となっています。
処分軽減のために出来ることは何か
まず、上司への暴言行為等についても、処分基準において処分対象として想定されています。パワハラ、といえるような行為について、上司から部下に対する者でなければならないということはありません。そして、処分基準としては、戒告、減給となっています。減給となってしまうと、より職場にいづらくなってしまう他、ボーナスなどへの影響も出てしまうので、出来るなら戒告程度にとどめたいものです。
また、本件は事案がある程度明白ですが、身に覚えがないのに上司に対して反逆した、職場内秩序を乱した、として懲戒の対象になってしまうことも有り得ます。
いずれにしろ、処分軽減のためには事案に至る経緯、事案の性質について、説得的な主張が出来るように整理することや、証拠を集めるなどすることが大切です。
主張整理や、証拠集めに関しては、ご自身で行うことができないわけではありませんが。弁護士に相談・依頼することによって、適切な見通しの提供、効果的な主張の組み立て、効率的な証拠収集が出来る可能性があります。ひとつひとつの差で、処分に違いが出る可能性も十分あります。
まとめ
パワハラ行為や職場内秩序の攪乱行為については、事実認定や評価が大きく処分に影響します。そのための主張や証拠整理が重要です。
処分軽減や、処分回避に関心がある方は、一度弁護士の相談に来ていただくことをお勧めします。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が、全力でサポートいたします。
無料法律相談受付中
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では弁護士による無料法律相談を行っています。
無料法律相談のご予約は
📞0120-631-881
または
✉お問合せフォーム
よりお問合せくださいませ。
公務員が万引き事件を起こしたら

公務員が万引き事件を起こしてしまったらすぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください
公務員は収入が安定しているので、万引きなどしないと思われるかもしれません。
しかし、万引きをする理由は生活苦だけではありません。
仕事やプライベートでのストレスを過剰に受け、精神が不安定になり、その結果として万引きを行ってしまう人がいます。
万引きをするときのスリルを感じることに依存してしまう状態となってしまいます。
なので、公務員といえども万引きをしてしまうことがあります。
公務員が万引きの犯罪をしてしまうと、自身に対する悪影響は大きなものになってしまいます。
逮捕されたら、その地位の重要性から、実名報道されてしまう可能性が一般の人より高くなります。
実名報道されたり、身体拘束が長くなってしまったら、勤務先に事件を知られてしまいます。
万引きは窃盗罪として、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金という重い刑罰に処されます(刑法第235条)。
厳しい懲戒処分を受け、懲戒免職となってしまうこともあります(「懲戒処分の指針について」第2 標準例 3 公務外非行関係 ⑺窃盗・強盗 ア)。
退職金も受け取れないことになるかもしれません。
事件を起こしてしまったら、慎重な対応が必要になります。
逮捕されたら、釈放を求めていくことになります。
証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを示し、検察や裁判所に釈放を訴えていくことになります。
しかし、釈放が認められるハードルは一般的には高く、難しいです。
そこで、刑事弁護に精通した弁護士に相談・依頼し、釈放を働きかけていくことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまでに多くの釈放を実現させてきました。
警察の取調べ対応を軽く見てはいけません。
警察が適正で公平な取調べをすると期待してはいけません。
実際に悪いことをしてしまったとしても、その悪質性を過剰に大きく見せるような内容の調書を作成しようとしてきます。
そのためには、怒鳴りつけたり、威圧したり、嘘を付いたり、話を盛ったり、等をして話をこちらに不当に不利に誘導してきます。
公務員とはいえ刑事手続きについて素人である一般人が、プロである警察に毅然と対応することは非常に難しいです。
そこで、刑事弁護に精通した弁護士に相談・依頼し、慎重に対応していく必要があります。
取調べでどのように話せばいいのか、問題が生じたときにどのように対応すればいいのか、等を具体的に打合せをして進めていくことになります。
被害店舗に対する示談・被害弁償交渉が必要になります。
状況次第では、被害店舗の人は感情的に責めてきて、冷静な話し合いが実現できなくなるかもしれません。
こちらが強く反省して申し訳ないという気持ちがあったとしても、伝え方によっては被害店舗の人の感情を逆なでして、逆効果になってしまうこともあります。
やはり、弁護士を通じて話し合う方がお互い冷静になれます。
誠意を持って話し合い、謝罪や示談・被害弁償の交渉をしていくことになります。
万引きの背景事情として精神疾患があるのであれば、治療をしていくことになります。
本人が反省したといくら言っても、精神の病気を改善させなければ、再び万引きを繰り返してしまうことになってしまいます。
精神科に受診し、治療を継続していただくことになります。
二度と万引きを繰り返さないようにし、根本的な問題の解決につなげます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、公務員の方の事件も万引き事件もこれまでに数多く扱って解決に導いてきました。
初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
有料の初回接見サービスにより、ご家族等からのご依頼でなるべく早く接見に向かいます。
迅速で慎重な対応が必要になりますので、万引き事件を起こしてしまったら早く弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
刑事弁護に精通した弁護士が対応いたします。
こちらの記事もご覧ください
公務員の懲戒処分について解説

公務員は全体の奉仕者であり、国民生活を守る立場にあります。このような公務員が違法・不当な行為をすることは、国民の信頼を裏切ることになります。公務員がこのような行為をした場合、懲戒処分を受けます。場合によっては懲戒免職と言う厳しい処分が下されます。
ここでは、公務員の懲戒処分について解説します。
懲戒処分
公務員の懲戒処分は、公務員が非違行為をした場合に行われます。犯罪に該当する場合はもちろん、その他職務上の義務に違反した場合も、対象となります。
公務員の懲戒処分に関して、国家公務員では、人事院が「懲戒処分の指針」を定めており、これに基づいて懲戒処分が行われます。
「懲戒処分の指針」では、懲戒処分の基本事項について以下のように定めています。
第1 基本事項
本指針は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の種類を掲げたものである。
具体的な処分量定の決定に当たっては、
① 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか
② 故意又は過失の度合いはどの程度であったか
③ 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか
④ 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか
⑤ 過去に非違行為を行っているか
等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものとする。
また、「第2 標準例」において、各非違行為の標準的な懲戒処分について定めています。
地方公務員については、各地方公共団体が懲戒処分の指針について定めており、これに基づいて懲戒処分が行われます。
重い懲戒処分について
公務員の懲戒処分は、職務の懈怠など犯罪に該当しない場合も行われます。しかし、やはり犯罪を行えば、重い懲戒反分が下されます。
窃盗
公務員がコンビニのセルフ式のコーヒーマシンで、支払った金額で注げるサイズより大きなサイズを注いで、警察に逮捕されたり懲戒免職処分を受けた事件が相次ぎ、話題となりました。
窃盗罪自体、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(刑法第235条)という、重い刑罰が定められている犯罪です。
人事院の「懲戒処分の指針」でも、「他人の財物を窃取した職員は、免職又は停職とする。」とされています。
痴漢・盗撮
痴漢行為や盗撮行為については、国家公務員の「懲戒処分の指針」では、停職又は減給と定められています。
しかし、地方公務員については、各地方公共団体の定める指針では、免職まで含めている場合が多いです。
実際の処分についても、近年では基本的に免職とされています。
刑罰としても、痴漢は態様によっては迷惑防止条例違反では済まず、不同意わいせつ(刑法第176条第1項第5号)にあたり、6月以上10年以下の拘禁刑という重い刑罰を科されます。
盗撮についても、迷惑防止条例違反だけでなく、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(性的姿態撮影処罰法)の違反(性的姿態等撮影罪)に該当すれば、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金という重い刑を科されます(同法第2条第1項)。
交通違反
交通違反の中でも、飲酒運転は特に重い懲戒処分が下されます。また、事故後の措置義務違反は、公務員が保身に走ったとして、重く処分されます。
国家公務員に関する「懲戒処分の指針」でも、
○酒酔い運転をした職員は、免職又は停職とする。この場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職とする。
○酒気帯び運転をした職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職又は停職(事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職)とする。
○飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員は、飲酒運転をした職員に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮して、免職、停職、減給又は戒告とする。
○人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において措置義務違反をした職員は、免職又は停職とする。
○人に傷害を負わせた職員は、減給又は戒告とする。この場合において措置義務違反をした職員は、停職又は減給とする。
と定められています。
飲酒運転や措置義務違反をすると、重い懲戒処分を下されます。
まとめ
このように、公務員の懲戒処分は、想像よりも重く定められています。
公務員の方で懲戒処分についてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
こちらの記事もご覧ください
増える飲酒運転での懲戒免職

公務員の方であれば、飲酒運転をすることが犯罪であること、近年刑罰も厳しくなっていっていること、懲戒のリスクを受けること自体はお分かりかと思います。さらに近年では、飲酒運転で懲戒免職までされるケースがかなり多く出始めている印象です。
今回は、飲酒運転で懲戒免職になった事例について紹介します。
実際の事例
(Yahoo!ニュース。令和7年6月23日閲覧。)
福島県伊達市は6月20日、職員2人の懲戒処分を行ったと公表した。
このうち22歳の女性主事は酒気帯び運転で物損事故を起こしたとして懲戒免職。
女性主事は1月25日に福島市内の市道で酒気を帯びた状態で自家用車を運転して電柱に衝突し、罰金35万円と2年間の運転免許取り消し処分となっている。
中略
須田博行伊達市長は「職員に対し、公務の内外を問わず公務員としての自覚を促すとともに、信頼回復に全力で取り組んでまいる」とコメントしている。
関係法令
酒気を帯びた状態で自動車を運転することが禁止されていること自体は、上記でも述べた通り明らかです。
刑事罰としては、3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金となります。さらに、運転免許に関しても違反点数が加算され、免許の停止、免許の取り消しがあります。
懲戒基準
当該福島県伊達市の懲戒基準は以下の通りです。
(令和7年6月23日閲覧)
飲酒運転による物損事故については、酒気帯びの場合免職又は停職となっています。
弁護活動
上記のように、飲酒運転の処分については、免職も定められていますが、停職で済む場合もあります。減給も選択肢にある自治体もありますし、自治体によっては近年になって減給の選択肢が無くなっていることも考えられます。基本的に、公務員の方が減給以上の処分になった場合、自主的に退職をすることが多いと考えられますが、免職の場合と比べれば退職金などの扱いが大きく異なることになります。
処分を決めるにあたっては、いつ飲酒したのか、どの程度飲酒したのか、その後の対応などが参考になると考えられます。弁護士がついていれば、何を言えば説得力があるか、メリットがあるかなど正確にアドバイスができます。
特に、酒気帯び運転などでは、上記でも説明したように処分の振れ幅があるので、綿密な準備をしてより軽い処分を目指していく意味が大きくなります。
まとめ
酒酔運転等の場合は、処分結果が免職ありきになるようなことも考えられますが、酒気帯び運転のアルコール数値等によっては免職を避けることができるかもしれません。
飲酒運転をしてしまって、懲戒処分を受けるのではないかとお悩みの公務員の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。相談を受けるだけでも、今後の方針を決めるのに役に立つはずです。
こちらの記事もご覧ください
公務員の違法薬物事件について

文部科学省や経済産業省といった日本の官僚機構の中枢において、エリート官僚が大麻や覚醒剤といった違法薬物を所持し、省内に捜索が行われたニュースは社会に衝撃を与えました。また、近年では大麻による検挙数が増加しており、警察官や自衛官からも逮捕者が出たり懲戒処分を受ける者も出ています。
ここでは、公務員の違法薬物事件について解説します。
違法薬物の規制
近年は覚醒剤関係事件の検挙数は減少していますが、大麻関係事件の検挙数は増加しています。
そのため、大麻は「麻薬及び向精神薬取締法(麻薬取締法)」の「麻薬」の一つとして、使用(施用)も処罰されるようになり、刑罰も他の麻薬と同様に重くなりました。
また、危険ドラッグと呼ばれる、大麻や覚醒剤などの違法薬物の成分を変えた薬物が問題になっており、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(薬機法)の指定薬物に定めることなどにより対処しています。
刑事処分
大麻やMDMAなどジアセチルモルヒネ(ヘロイン)等以外の麻薬をみだりに所持した場合、7年以下の拘禁刑に処されます(麻薬取締法第66条第1項)。営利目的の場合、1年以上10年以下の拘禁刑又はこれに加えて300万円以下の罰金が科されます(第2項)。使用(施用)した場合も、7年以下の拘禁刑に処されます(麻薬取締法第66条の2第1項・第27条第1項)。営利目的の場合、1年以上10年以下の拘禁刑又はこれに加えて300万円以下の罰金が科されます(第2項)。
薬機法の指定薬物を所持したり使用した場合は3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれらの刑が併科されます(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第84条第28号・第76条の4)。
覚醒剤を所持や使用した場合は、10年以下の拘禁刑に処されます(覚醒剤取締法第41条の2第1項、第41条の3第1項第1号・第19条)。営利目的でこれらの行為を行った場合、1年以上の拘禁刑が科され、又はこれに加え500万円以下の罰金が科されます(第41条の2第2項、第41条の3第2項)。覚醒剤を輸入・輸出や製造をすると、1年以上の拘禁刑に処され(第41条第1項)、営利目的で行った場合は無期若しくは3年以上の拘禁刑に処され、又はこれに加えて1000万円以下の罰金に処されます(第41条第2項)。
ジアセチルモルヒネ(ヘロイン)等の麻薬についても覚醒剤と同様処罰されます。これらの麻薬を輸入・輸出や製造をすると、1年以上の拘禁刑に処され(麻薬取締法第64条第1項)、営利目的で行った場合は無期若しくは3年以上の拘禁刑に処され、又はこれに加えて1000万円以下の罰金に処されます(第64条第2項)。これらの麻薬をみだりに製剤や所持、使用(施用)した場合は、10年以下の拘禁刑に処されます(第64条の2第1項、第64条の3第1項)。営利目的でこれらの行為を行った場合、1年以上の拘禁刑が科され、又はこれに加え500万円以下の罰金が科されます(第64条の3第2項)。輸入・輸出や製造をすると、1年以上の拘禁刑に処され(第64条第1項)、営利目的で行った場合は無期若しくは3年以上の拘禁刑に処され、又はこれらに加えて1000万円以下の罰金に処されます(第64条第2項)。
裁判では初犯の場合、大麻等の麻薬や指定薬物に関する違反の場合は6月から1年の拘禁刑・2年から3年の執行猶予、覚醒剤やヘロイン等の悪質な違法薬物に関する違反の場合は拘禁刑1年6月程度・執行猶予3年程度となることが多いです。
また、薬物使用等の罪の一部については、「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律」により、刑の一部執行猶予(刑法第27条の2)の特則が定められており、前に刑の全部の執行を猶予されたことなどの条件(刑法第27条の2第1項各号)を満たしていなくても、「刑事施設における処遇に引き続き社会内において・・・規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが」再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ相当と認められるときは、刑の一部の執行を猶予することができます。具体的には、初めは刑務所で服役し、刑期の終盤に執行猶予として社会に出て、保護観察を受けながら社会復帰を目指すことになります。
懲戒処分
公務員に違法薬物の所持などの非違行為があれば、刑罰だけでなく、懲戒処分も受けることになります。
国家公務員の場合、懲戒処分は任命権者が行いますが、懲戒手続は人事院が行います(国家公務員法84条1項2項)。
地方公務員の場合は、条例に定められた機関が懲戒手続を行います(地方公務員法29条4項)。
人事院の「懲戒処分の指針」によれば、国家公務員が大麻や覚醒剤などの違法薬物を所持していれば、「公務外非行関係」の「(10)麻薬等の所持等」に該当し、必ず免職処分となります。
地方公務員の場合も同様に重い懲戒処分が下されます。例えば、東京都だと、麻薬又は覚醒剤等を所持又は使用した職員は、免職としています。薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)や東京都の条例の指定する薬物、いわゆる危険ドラッグを所持又は使用した場合も免職又は停職としています(東京都知事部局「懲戒処分の指針」参照)。
刑事手続との関係
懲戒処分のような行政処分も、事実に基づいて行われます。逮捕や勾留され、本人も違法薬物の所持や使用を認めている場合は、捜査中であったり起訴され判決が出る前であっても懲戒処分が下されることがありますが、公務員が違法薬物を所持・使用等したとして捜査されている間は、本人が否認していたり途中で捜査手続きに問題があることが明らかになるようなこともあるため、基本的には刑事手続の終了を待って処分が下されるでしょう。
また、大麻等ではよく見られますが、所持していたことが証拠上明らかであってもその量が微量の場合は、不起訴となることがあります。このように刑事手続上は処罰されなかった場合でも懲戒手続が進められます。
公務員の場合、起訴されると、強制的に休職させられることがあります(地方公務員法第28条第2項第2号、国家公務員法第79条第2号)。裁判の結果、有罪の判決を言い渡され、禁錮(改正後の拘禁刑も含まれます)以上の刑に処されると、失職となります(地方公務員法第28条第4項・第16条第1号、国家公務員法第条第76条・第38条第1号)。
懲戒手続自体は、刑事裁判が継続中の事件であっても懲戒手続を進めることができる旨が国家公務員法に定められています(国家公務員法第85条)。
まとめ
このように、公務員が違法薬物を所持したり使用したりすると、大変重い懲戒処分や刑罰を受けることになります。
公務員の方で違法薬物にお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
こちらの記事もご覧ください
公務員の痴漢事件について

公務員が痴漢をしてしまったらすぐにご相談ください
公務員が痴漢で逮捕されたとのニュースが少なくありません。
公務員という地位の重要性から、実名報道されることが多いです。
職場にばれ、懲戒処分を受けることになります。
公務員が痴漢をしてしまったら、その悪影響は大きいものになります。
事件が起きてしまったら、迅速に慎重な対応が必要になります。
条例違反としての痴漢
痴漢は、基本的には各地方公共団体の条例に罰則が規定されております。
お尻を触ったりする痴漢行為が想定されております。
正当な理由なく、公共の場所・乗物で、衣服の上や直接身体に触れたら、犯罪として処罰されることになります。
常習性があれば、より重く処罰されます。
電車内で女性のお尻を触る痴漢行為等で適用されることが多いです。
不同意わいせつ罪
女性の胸を揉む等、侵害の程度が大きいと、不同意わいせつ罪が成立することになります。
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、不同意わいせつ罪が成立します(刑法第176条第1項)。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、不同意わいせつ罪が成立します(同条第2項)。
16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、相手の同意は無効とされ、不同意わいせつ罪が成立します(同条第3項)。
未遂も罰せられます(刑法第180条)。
不同意性交等罪
更に、例えば女性器の中に指を入れる行為をしたら、不同意わいせつ罪より更に罪が重い不同意性交等罪が成立します。
不同意わいせつ罪に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものである性交等をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、不同意性交等罪が成立します(刑法第177条第1項)。
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、不同意性交等罪が成立します(同条第2項)。
16歳未満の者に対し、性交等をした者も、相手の同意は無効とされ、不同意性交等罪が成立します(同条第3項)。
未遂も罰せられます(刑法第180条)。
取調べ対応は慎重に
捜査機関の取調べが適正公平に行われると期待してはいけません。
特に警察は、威圧しますし、脅してきます。
嘘も付いてきますし、話を盛ったりします。
違法・不当な取調べにより、こちらに不利な方向で話を持っていき、調書が作成されてしまいます。
公務員とはいえ刑事事件に関して素人の一般人が、プロの警察官に対して毅然とした対応をすることは難しいです。
刑事弁護に精通した弁護士を立てて、慎重に対応する必要があります。
被害者への示談活動が重要
被害者に対しては、迅速に誠意を持って対応していかなければなりません。
しかし、痴漢をした本人が被害者に直接接触することはできません。
弁護士を立てて、捜査機関を通じて接触を試み、話し合いをしていくことになります。
謝罪のうえで被害弁償の支払いをし、示談を求めていくことになります。
二度と接触しない、等の条項についても話し合い、示談書面に記載することになります。
公務員が痴漢事件を行ってしまったら,すぐに弁護士に相談してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,公務員による痴漢事件をこれまで多数扱ってきました。
取調べ対応,釈放活動,示談活動,公判対応,等について経験豊富で,具体的にどのように対応すればいいか心得ております。
0120-631-881までお電話してください。
初回面談は無料です。
有料の初回接見をご希望のご家族等は,依頼していただけたらすぐに対応いたします。
スピードが重要ですので,ぜひお早めにご連絡ください。
こちらの記事もご覧ください
公務員の性的逸脱行為への制裁
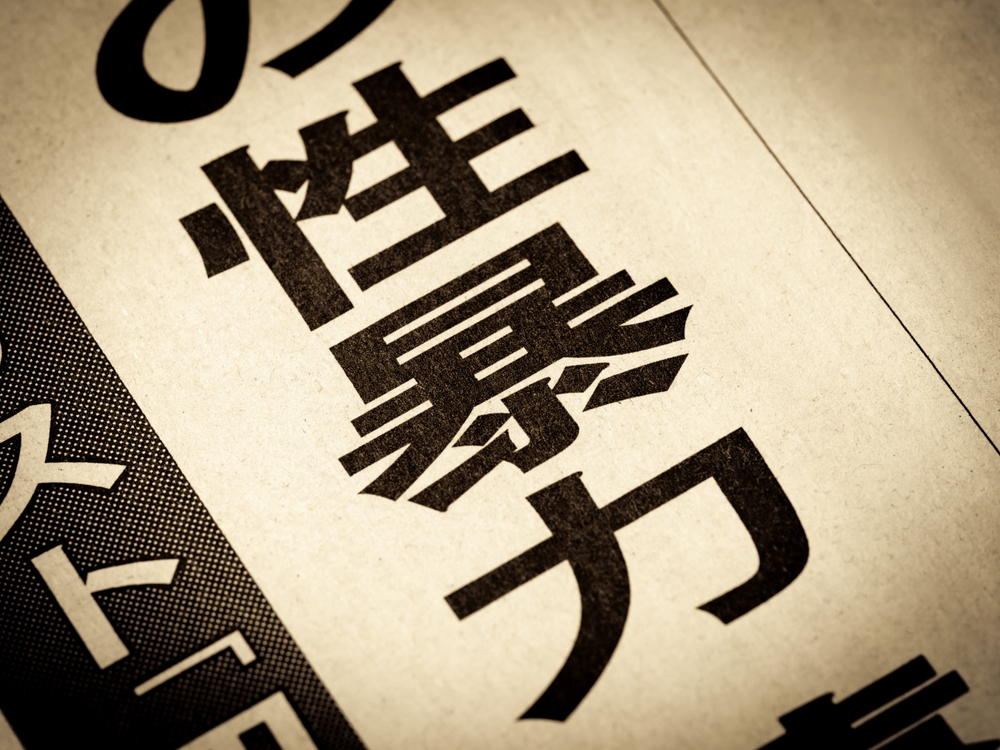
公務員の性的逸脱行為
学校の教師が生徒に対し性交等をしたり盗撮をするといった性犯罪が発覚し、問題となっています。国公立学校の場合、教師は公務員ですので、公務員としての懲戒処分を受けます。
ここでは、公務員の性的逸脱行為についての刑罰や懲戒処分について解説します。
性犯罪
公務員に問題となる性犯罪としては、以下のものがみられます。
不同意わいせつ・不同意性交等
公務員や学校の教師の地位を利用した犯罪としては、不同意わいせつ罪(刑法第176条)や不同意性交等罪(刑法第177条)が問題となります
公務員としての立場や、教師が生徒に対して行う場合、相手は逆らうとどのような不利益を受けるかと委縮して不同意を示せなくなると考えられます。これは「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること」(刑法第176条第1項第8号)に当たる可能性があります。
また、相手が16歳未満の者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限ります)の場合、この様な事由に関わらず、不同意わいせつや不同意性交等に該当します(刑法第176条第3項、刑法第177条第3項)。
職務外での性犯罪
職務外で起こし得る性犯罪としては、痴漢や盗撮があります。
痴漢は各都道府県の迷惑防止条例違反や不同意わいせつ罪に当たります。胸や性器を触るなど悪質な場合は不同意わいせつ罪となります。
盗撮は各都道府県の迷惑防止条例違反や性的姿態等撮影罪(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第2条)となります。被害者が18歳未満の児童の場合、児童ポルノ製造罪(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第7条第5項)にも該当します。
また、18歳未満の児童を買春(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条第2項)した場合、児童買春(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条)に該当します。
性犯罪関係の懲戒処分
公務員が性犯罪やわいせつ行為をすると、非違行為をしたとして、重い懲戒処分を受けることになります。
国家公務員の懲戒に関する、人事院の「懲戒処分の指針について」によると、「3 公務外非行関係」において、「(12)淫行」では、18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行した職員は、免職又は停職とする、と定めています。また、「(13)痴漢行為」「(14)盗撮行為」も停職又は減給という比較的重い処分となっています。
また、地方公務員については、各地方公共団体の機関が懲戒処分の指針を定めています。
自身の職務に関し、その職務上の立場を悪用した非違行為ほど、厳しい処分がされます。
例えば、「さいたま市教員の懲戒処分の指針」の「5 児童生徒に対する非違行為関係」では、「(2) 児童生徒性暴力等」「ア 職務上関係のある、あるいは関係のあった児童生徒に対してわいせつな行為をした教職員は、免職とする。」「ウ 職務上関係のある、あるいは関係のあった児童生徒に対してわいせつな言辞等の性的な言動等不適切な行為を行った教職員は、停職又は減給とする。この場合において不適切な行為が特に悪質なときは、当該教職員は免職とする。」などと定められています。
その他、18歳以上の者の売買春は、犯罪ではありませんが違法であり(売春防止法第3条)、品位を害するものとして懲戒処分の対象となり得ます。
公務員の身分に関する手続き
上記のように、性犯罪やわいせつな行為に対しては重い懲戒処分が下されます。
公務員の場合、起訴されると、強制的に休職させられることがあります(地方公務員法第28条第2項第2号、国家公務員法第79条第2号)。休職中は仕事ができませんし、給与は支給されません(国家公務員法第80条第4項参照)。
国家公務員法では、刑事裁判が継続中の事件であっても懲戒手続を進めることができる旨定められています(国家公務員法第85条)。そのため、起訴されたり判決が出る前に懲戒手続がすすめられ、懲戒処分が下されることがあります。例えば、逮捕勾留中に教育委員会の委員が拘束下にいる教師と接見して事情聴取し、非違行為があったと認められれば、懲戒処分を下します。
裁判の結果、有罪の判決を言い渡され、禁錮以上の刑に処されると、失職してしまいます(地方公務員法第28条第4項・第16条第1号、国家公務員法第76条・第38条第1号)。地方公務員の場合は、「条例に特別の定めがある場合」には失職とならないとすることができます。しかし、通勤中の交通事故や執行猶予付きの禁錮にとどまる場合にのみ失職させないことができるという場合が多いです。性犯罪の場合、懲役刑が多いですし、上記のように事案によっては免職となるほど重いとみなされている類型であるため、原則通り失職することになるでしょう。
まとめ
このように、公務員の性犯罪は重い処分が下されることになります。性犯罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
こちらの記事もご覧ください。
インターネットの未成年者への性犯罪

公務員によるインターネットを通じた未成年者に対する性犯罪
インターネットは簡単に利用できることから、軽い気持ちで未成年者に対する性犯罪を行ってしまう公務員の方がいます。
インターネットを通じて、裸の写真や動画を送るように要求したり、実際に会って性交等をすることを要求するケースが少なくありません。
発覚したら、警察がある日突然自宅に来て、逮捕されることもあります。
逮捕されたら、公務員という地位の重要性から、実名報道されてしまう可能性が一般の人より高くなってしまいます。
勤務先に知られてしまったら、懲戒免職を受け、失職することになるかもしれません。
公務員という身分から、一般の人より悪影響が大きくなってしまうので、迅速で慎重な対応が求められます。
<16歳未満の者に対する面会要求等罪>
わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処されます(刑法第182条第1項)。
一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
前記の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処されます(第2項)。
16歳未満の者と実際に会って、性交等をしたら不同意性交等罪が成立して5年以上の有期拘禁刑に処され、わいせつ行為をしたら不同意わいせつ罪が成立して6月以上10年以下の拘禁刑に処されます。
<16歳未満の者に対する映像送信要求罪>
16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為を要求した者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処されます(刑法第182条第3項)。
一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。
実際に撮影させて送らせたら、不同意わいせつ罪、性的姿態等撮影罪、児童ポルノ製造罪等が成立することになります。
<児童買春罪>
18歳に満たない児童に対して児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されます(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条・第2条)。
児童買春とは、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいいます。
ここでいう性交等とは、性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。
金銭の供与がないのであれば、各地方公共団体が定める淫行条例違反が成立することになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、公務員による犯罪事件の刑事弁護の実績が豊富な事務所です。
専門の弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元会計検査院の官房審議官など、公務員による犯罪事件に力強く対応することができる専門知識が豊富な弁護士が在籍しております。
公務員による犯罪事件に強い弁護士が、刑事事件化を阻止したり、逮捕勾留を阻止したり、不起訴によって刑事裁判を回避したり、刑事裁判で無罪主張や減刑・罰金減額の主張をしたり、お悩みのあなたを迅速・丁寧にサポートいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、どんなに厳しい事件でも、依頼者の人生が好転して前向きになれるよう、全力でサポートいたします。
まずは無料相談を受けてみてください。
迅速な対応が求められますので、ぜひお気軽にご連絡ください。
こちらの記事もご覧ください
公務員の副業と懲戒処分
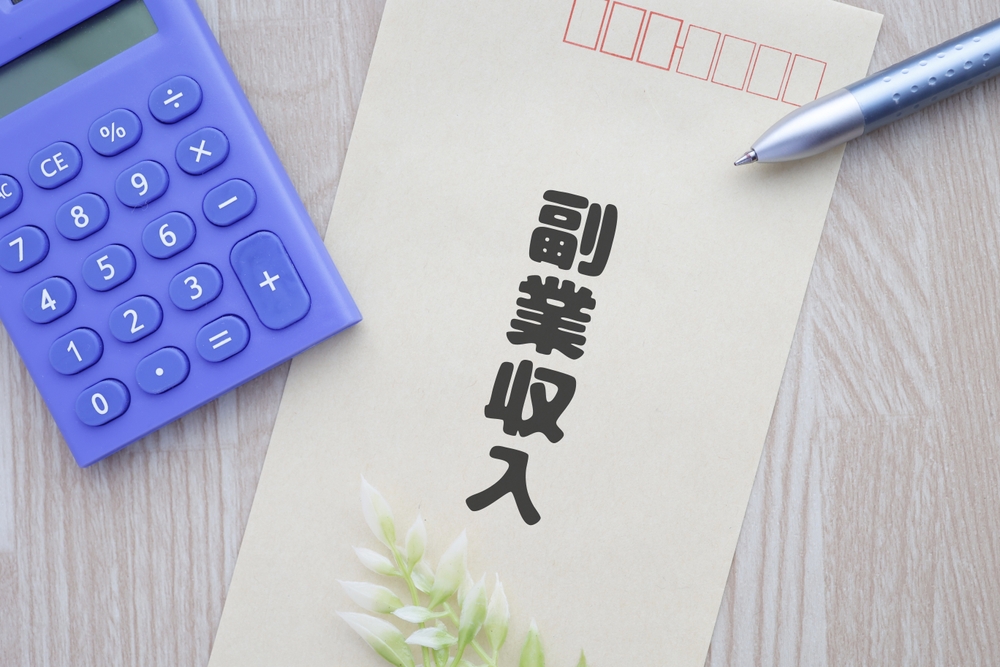
公務員は全体の奉仕者であり、その職務に専念するべき立場にあります。そのため、公務員には職務専念義務が定められています。このような公務員が許可なく副業をすれば、懲戒処分を受けます。事案によっては、減給など重い処分を受けることもあります。
ここでは、公務員が許可なく副業をした場合について解説します。
職務専念義務
職務専念義務は、国家公務員法、地方公務員法に定められています。公務員は、法律や命令、条例に特別の定めがある場合を除いて、副業(兼業)が禁止されています。
国家公務員法第101条第1項
職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。職員は、官職を兼ねる場合においても、それに対して給与を受けてはならない。
地方公務員法第35条
職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
懲戒処分
公務員の懲戒処分は、国家公務員については、人事院が「懲戒処分の指針」を定めており、これに基づいて懲戒処分が行われます。
地方公務員の懲戒処分については、各地方公共団体が懲戒処分の指針や基準を定めており、これに基づいて懲戒処分が行われます。
国家公務員についての「懲戒処分の指針」では、懲戒処分の基本事項について以下のように定めています。
第1 基本事項
本指針は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の種類を掲げたものである。
具体的な処分量定の決定に当たっては、
① 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか
② 故意又は過失の度合いはどの程度であったか
③ 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか
④ 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか
⑤ 過去に非違行為を行っているか
等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものとする。
副業の禁止
許可なき副業(兼業)の禁止は、「懲戒処分の指針」の「第2 標準例」の「1 一般服務関係」において定められています。減給処分もあり得ます。
第2 標準例
1 一般服務関係
(10) 兼業の承認等を得る手続のけ怠
営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った職員は、減給又は戒告とする。
副業禁止違反となる場合
副業禁止違反となる事案として、実家の家業を手伝ってお金を受取っていた場合などがあります。
公立病院に勤務する医師が他の病院で勤務して報酬を得ている場合も、副業と判断されます。
また、メルカリ等で自身の持ち物を転売する行為も、転売する物を他所から仕入れたり、反復継続して行っていると、副業と判断される場合もあります。
公務員としての仕事以外でお金を得るような場合は注意が必要です。
また、これにより得た収入を隠して、公務員としての給与だけで確定申告をすると、脱税となり、所得税法違反などに問われることになります。このような脱税も懲戒事由となります。
まとめ
このように、公務員の副業は、想像よりも大変な事態になりかねません。 公務員の方で、公務員としての給与以外でお金を得ていて、副業禁止違反にならないか不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
こちらの記事もご覧ください
公務員と副業-公務員が副業をした場合の懲戒手続きについて解説
自転車の飲酒運転と公務員の懲戒処分

道路交通法の改正により、自転車の飲酒運転が罰則の対象になりました。
今後は、自転車であっても、アルコールを保有している状態で運転したら、犯罪となり、刑事処分を受けることになります。
通勤で自転車を利用している公務員の方が、仕事終わりに飲食をしてアルコールを飲み、そのまま帰宅をするときに自転車を使用したら、犯罪となります。
自動車でなく自転車だからまあいいか、という考えで運転してしまったら、犯罪が成立して刑事処分を受けるだけでなく、勤務先から懲戒処分も受けることになってしまいます。
特に、公務員に対しては飲酒運転に関して厳しい懲戒処分をしてくることが予想され、その悪影響は大きいものとなります。
何人も、酒気を帯びて自転車を含めた車両等を運転してはなりません。
違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったら、酒気帯び運転として3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処されることになります。
政令で定める程度は、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムとされています。
違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態にあったら、酒酔い運転として5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処されることになります。
酒に酔った状態とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。
また、飲酒運転をするおそれがある人に対して、自転車を提供したり、酒類の提供や飲酒を勧める行為をしたりする行為も、犯罪となります。
国家公務員を対象にした「懲戒処分の指針について(平成12年3月31日職職―68)(人事院事務総長発)」によると、酒気帯び運転をした職員は免職・停職・減給、酒酔い運転をした職員は免職・停職と示されております。
具体的な処分量定の決定に当たっては、
① 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか
② 故意又は過失の度合いはどの程度であったか
③ 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか
④ 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか
⑤ 過去に非違行為を行っているか
等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものとされております。
より重いものとすることが考えられる場合として、
① 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき
② 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき
③ 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき
④ 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき
⑤ 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき
があるとされております。
より軽いものとすることが考えられる場合として、
① 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき
② 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき
があるとされております。
地方公務員に関しては、各地方公共団体ごとに懲戒処分の指針が定められております。
刑事処分や懲戒処分の判断に当たっては、具体的な犯罪行為の内容の確認が必要になります。
警察の取調べや職場での聞き取りでは、よりこちら側に悪い方向で話を誘導されてしまうことがあります。
そうなると、より重い処分を受けることになってしまいます。
弁護士を立てて、取調べや聞き取りに対して慎重な対応をしていく必要があります。
そのうえで、検察や職場に対して意見書を提出し、犯罪の内容の悪質性が過剰に評価されないように働きかけていくことになります。
そのうえで、反省や更生の意思と再犯防止策を示していくことになります。
アルコールに対して依存性が認められるのであれば、病院へ受診・通院して治療を進める必要があります。
家族等に飲酒運転をさせないように今後監督していくことを誓ってもらうことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまでに多数の公務員の方の犯罪事件の相談・依頼を受け、解決に導いてきました。
公務員が自転車の飲酒運転をしてしまい、警察の捜査・取調べを受けることになったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にぜひご相談ください。
迅速で慎重な対応が必要であり、初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
こちらの記事もご覧ください
公務員の飲酒運転-公務員が飲酒運転をしたときに成立する犯罪や懲戒処分について解説
« Older Entries