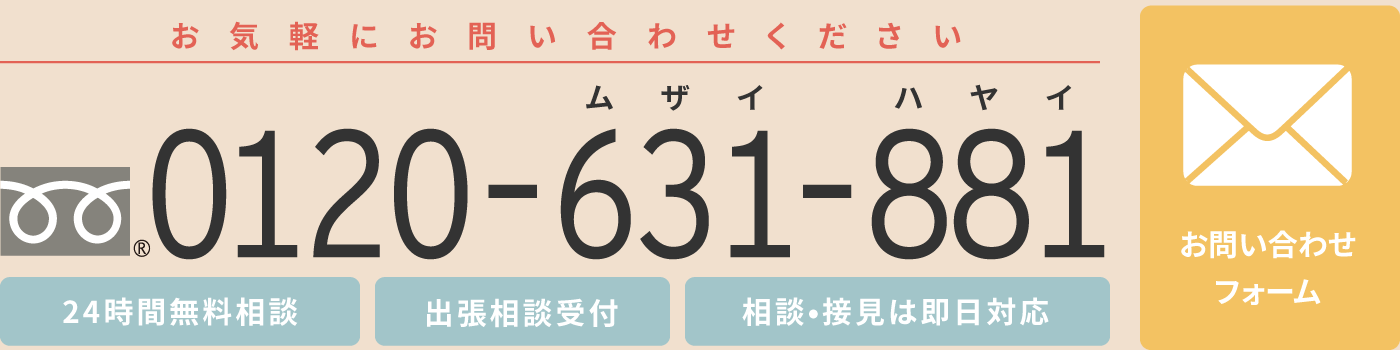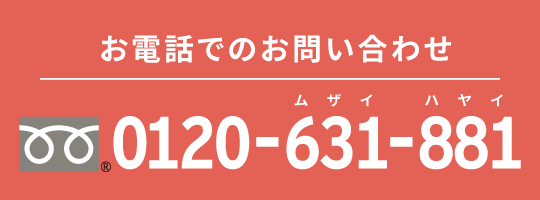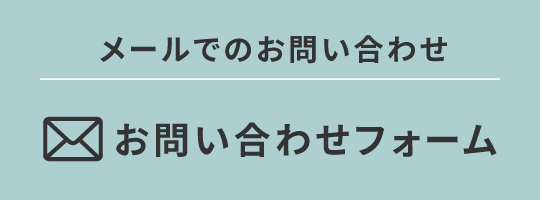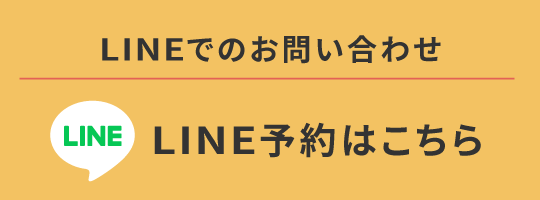公務員は全体の奉仕者として公正中立でなければなりません。そのため、公務員には一般市民と異なる様々な規制があります。特に労働基本権である争議行為の禁止と表現の自由にかかわる政治活動の禁止は非常に大きな制約です。ここでは、公務員に特に課せられている制限について解説します。
服務規律
国家公務員法では「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と定めています(国家公務員法第96条第1項)。これを果たすため、様々な服務規律が定められています。
信用失墜行為の禁止(第99条)や秘密を守る義務(第100条)、職務に専念する義務(第101条)などは当然順守するべきと考えられますが、それ以上の制約があります。
争議行為等の禁止
「職員は、政府が代表する使用者としての公衆に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。」(第98条第2項)、「職員で同盟罷業その他前項の規定に違反する行為をした者は、その行為の開始とともに、国に対し、法令に基いて保有する任命又は雇用上の権利をもつて、対抗することができない。」(第98条第3項)と定め、争議行為等を禁止しています。
これらの争議行為をすることだけでは刑罰を受けませんが、「何人たるを問わず第九十八条第二項前段に規定する違法な行為(政府が代表する使用者としての公衆に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為)の遂行を共謀し、唆し、若しくはあおり、またはこれらの行為を企てた者」は3年以下の禁錮又は100万円以下の罰金に処されます(第111条の2第1号)。
いわゆる全農林警職法事件(昭和48年4月25日最高裁大法廷判決)において、最高裁は、公務員の地位の特殊性や職務の公共性から公務員が争議行為に及ぶことは国民全体の共同利益に重大な影響を及ぼすこと、公務員の勤務条件は国民の代表者により構成される国会の制定した法律・予算によって民主的に定められるものであり争議行為により強制する圧力をかけることは民主的に行われるべき手続きを歪めるおそれがあること、私企業の労働者の場合と異なり市場の抑制力が働かないこと、国際労働機構(ILO)の条約でも公務員の地位の特殊性を認めてストライキの禁止を認めていること、などを理由に、公務員の争議行為の制約の必要を認めています。一方で、団体交渉権は認められていること、単に争議行為に参加したに過ぎない者には罰則はないなど、公務員の労働基本権を尊重し、制約を最小限にしていると指摘しました。そして、公務員に対しては、このような制約の代償措置として、勤務条件が法定され、また準司法機関的性格を持つ人事院による勤務条件の報告、人事院に対する行政措置や審査請求ができると指摘しています。このようなことから、「公務員の従事する職務には公共性がある一方、法律によりその主要な勤務条件が定められ、身分が保障されているほか、適切な代償措置が講じられているのであるから、国公法九八条五項がかかる公務員の争議行為およびそのあおり行為等を禁止するのは、勤労者をも含めた国民全体の共同利益の見地からするやむをえない制約というべきであつて、憲法二八条に違反するものではない」としました。また、「公務員の争議行為の禁止は、憲法に違反することはないのであるから、何人であつても、この禁止を侵す違法な争議行為をあおる等の行為をする者は、違法な争議行為に対する原動力を与える者として、単なる争議参加者にくらべて社会的責任が重いのであり、また争議行為の開始ないしはその遂行の原因を作るものであるから、かかるあおり等の行為者の責任を問い、かつ、違法な争議行為の防遏を図るため、その者に対しとくに処罰の必要性を認めて罰則を設けることは、十分に合理性があるものということができる。」として、当時の国家公務員法第110条1項7号(現第111条の2第1号)は憲法第18条、第28条に違反するものではないとしました。
政治的行為の制限
国家公務員法では、「職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。」(第102条第1項)、「職員は、公選による公職の候補者となることができない。」(第102条第2項)、「職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。」(第102条第3項)と定め、公務員の政治的行為を制限しています。
政治的目的や政治的行為については、人事院規則により定められています(人事院規則14-7)。
以上の行為のうち、第102条第1項に規定する政治的行為の制限に違反した場合、3年以下の禁錮又は100万円以下の罰金に処されます(第111条の2第2号)。
いわゆる猿払事件上告審判決(昭和49年11月6日最高裁大法廷判決)において、最高裁は「公務員の政治的中立性を損うおそれのある公務員の政治的行為を禁止することは、それが合理的で必要やむをえない限度にとどまるものである限り、憲法の許容するところであるといわなければならない。」とし、政治的行為を自由放任すると、公務員の政治的中立性が損なわれ、行政の中立的運営がゆがめられ、行政内の政治的対立により行政の能率的で安定した運営は阻害され、議会制民主主義の政治過程を経て決定された国の政策の忠実な実行にも重大な支障をきたす虞があること、もはや組織の内部規律の身によっては弊害を防止できないことなどから、「このような弊害の発生を防止し、行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼を確保するため、公務員の政治的中立性を損うおそれのある政治的行為を禁止することは、まさしく憲法の要請に応え、公務員を含む国民全体の共同利益を擁護するための措置にほかならないのであつて、その目的は正当なものというべきである。また、右のような弊害の発生を防止するため、公務員の政治的中立性を損うおそれがあると認められる政治的行為を禁止することは、禁止目的との間に合理的な関連性があるものと認められるのであつて、たとえその禁止が、公務員の職種・職務権限、勤務時間の内外、国の施設の利用の有無等を区別することなく、あるいは行政の中立的運営を直接、具体的に損う行為のみに限定されていないとしても、右の合理的な関連性が失われるものではない。」としました。
一方で、公務員の政治的行為を禁止すると意見表明の自由も制約することになりますが、「それは、単に行動の禁止に伴う限度での間接的、付随的な制約に過ぎず、かつ、国公法一〇二条一項及び規則の定める行動類型以外の行為により意見を表明する自由までをも制約するものではなく、他面、禁止により得られる利益は、公務員の政治的中立性を維持し、行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼を確保するという国民全体の共同利益なのであるから、得られる利益は、失われる利益に比してさらに重要なものというべきであり、その禁止は利益の均衡を失するものではない。」としました。
そして、この事件で問題とされていた人事院規則の「政治的目的の定義」と「政治的行為の定義」については、「政治的行為の中でも、公務員の政治的中立性の維持を損うおそれが強いと認められるものであり、政治的行為の禁止目的との間に合理的な関連性をもつものであることは明白である。また、その行為の禁止は、もとよりそれに内包される意見表明そのものの制約をねらいとしたものではなく、行動のもたらす弊害の防止をねらいとしたものであつて、国民全体の共同利益を擁護するためのものであるから、その禁止により得られる利益とこれにより失われる利益との間に均衡を失するところがあるものとは、認められない。したがつて、国公法一〇二条一項及び規則五項三号、六項一三号は、合理的で必要やむをえない限度を超えるものとは認められず、憲法二一条に違反するものということはできない。」としました。
罰則についても、「その保護法益の重要性にかんがみるときは、罰則制定の要否及び法定刑についての立法機関の決定がその裁量の範囲を著しく逸脱しているものであるとは認められない。特に、本件において問題とされる規則五項三号、六項一三号の政治的行為は、特定の政党を支持する政治的目的を有する文書の掲示又は配布であつて、前述したとおり、政治的行為の中でも党派的偏向の強い行動類型に属するものであり、公務員の政治的中立性を損うおそれが大きく、このような違法性の強い行為に対して国公法の定める程度の刑罰を法定したとしても、決して不合理とはいえず、したがつて、右の罰則が憲法三一条に違反するものということはできない。」としました。
まとめ
以上の通り、国民生活への影響の重大性、公務員の政治的中立性、民主的に定められた政策の誠実な実行といった重大な観点から、公務員の自由にも制約が課されており、違反によっては刑に処されます。