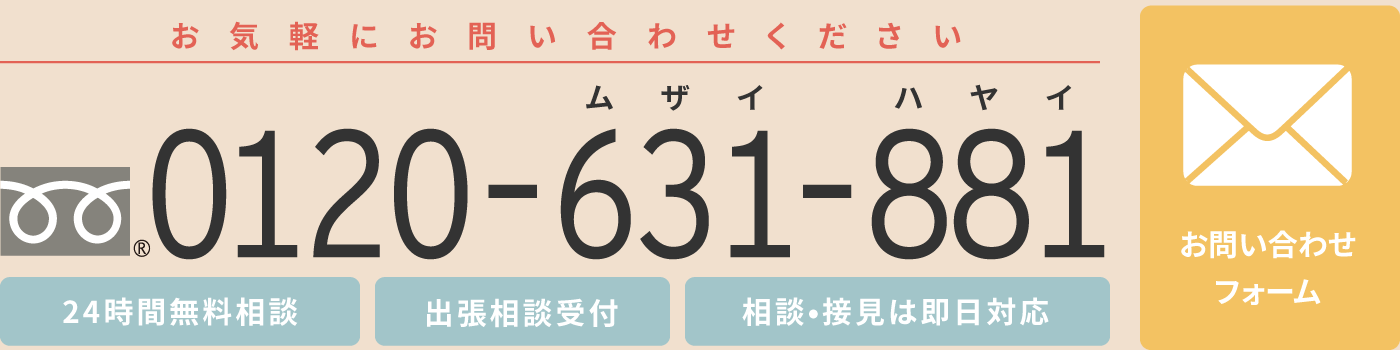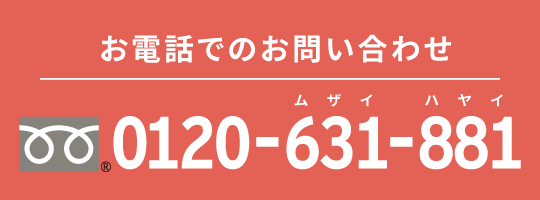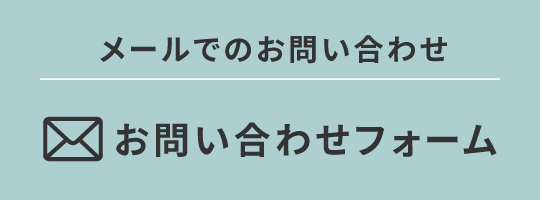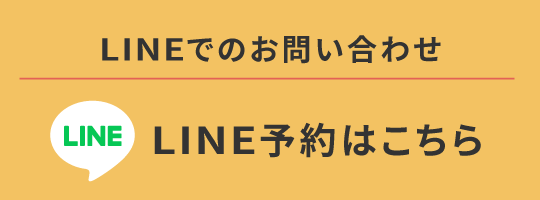Archive for the ‘懲戒処分等’ Category
公務員と児童に対する性犯罪-公務員が児童にわいせつな行為をした場合に成立する犯罪について解説

区立中学校の校長が教え子のわいせつ画像を所持していたとして起訴されるなど、教育関係者の性犯罪が問題となっています。国公立の学校の教職員は公務員であるため、公務員として懲戒処分の対象となります。
ここでは、教育に携わる公務員の性犯罪について解説します。
児童に対する性犯罪
児童に対する性犯罪としては、以下のものが多くみられます。
・不同意わいせつ(刑法第176条)
・不同意性交等(刑法第177条)
・性的姿態等撮影罪(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(性的姿態撮影等処罰法)第2条)
・児童に淫行をさせる行為(児童福祉法第34条第1項第6号)
・児童買春(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ法)第4条)
・児童ポルノ所持、提供等(児童ポルノ法第7条)
不同意わいせつ・不同意性交等、性的姿態等撮影罪
令和5年7月13日より改正刑法が施行され、強制わいせつ罪は不同意わいせつ罪に、強制性交等罪は不同意性交等罪に改められました。この改正により、暴行・脅迫による場合だけでなく、不同意を示せないような状況を強いられてわいせつ行為や性交等をされた被害者も保護できるようになりました。また、同日に性的姿態撮影等処罰法が施行され、盗撮行為がより重く処罰されるようになりました。いずれも、被害者が13歳未満の場合又は被害者が13歳以上16歳未満で行為者が被害者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者である場合は、不同意を示せない事由の有無等にかかわらず、犯罪が成立します(刑法第176条第3項・第177条第3項、性的姿態撮影等処罰法第2条第1項第4号)。
性犯罪関係の懲戒処分
公務員が性犯罪やわいせつ行為をすると、非違行為をしたとして、重い懲戒処分を受けることになります。
国家公務員の懲戒に関する、人事院の「懲戒処分の指針について」によると、「3 公務外非行関係」において、「(12)淫行」では、18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行した職員は、免職又は停職とする、と定めています。また、「(13)痴漢行為」「(14)盗撮行為」も停職又は減給という比較的重い処分となっています。
参照
また、地方公務員については、各地方公共団体の機関が懲戒処分の指針を定めています。
自身の職務に関し、その職務上の立場を悪用した非違行為ほど、厳しい処分がされます。
例えば、千葉県教育委員会の「懲戒処分の指針」の「3 児童生徒に対する非違行為関係」の「(2)わいせつな行為等」では、「・児童生徒に対してわいせつな行為を行った職員は、免職とする。」「・児童生徒に対してわいせつな言辞等の性的な言動を行った職員は、停職又は減給とする。ただし、性的な言動を執拗に繰り返すなど特に悪質な場合は、免職とする。」と定められています。
参照
公務員の身分に関する手続き
上記のように、性犯罪やわいせつな行為に対しては重い懲戒処分が下されます。
公務員の場合、起訴されると、強制的に休職させられることがあります(地方公務員法第28条第2項第2号、国家公務員法第79条第2号)。休職中は仕事ができませんし、給与は支給されません(国家公務員法第80条第4項参照)。
国家公務員法では、刑事裁判が継続中の事件であっても懲戒手続を進めることができる旨定められています(国家公務員法第85条)。そのため、起訴されたり判決が出る前に懲戒手続がすすめられ、懲戒処分が下されることがあります。
裁判の結果、有罪の判決を言い渡され、禁錮以上の刑に処されると、失職してしまいます(地方公務員法第28条第4項・第16条第1号、国家公務員法第条第76条・第38条第1号)。地方公務員の場合は、「条例に特別の定めがある場合」には失職とならないとすることができます。しかし、通勤中の交通事故や執行猶予付きの禁錮にとどまる場合にのみ失職させないことができるという場合が多いです。性犯罪の場合、懲役刑が多いですし、上記のように事案によっては免職となるほど重いとみなされている類型であるため、原則通り失職することになるでしょう。
こちらの記事もご覧ください。
まとめ
このように、公務員の性犯罪は重い処分が下されることになります。性犯罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
公務員の人身事故と弁護活動-公務員が人身事故を起こした場合の弁護活動について詳しく解説

【事例(フィクション)】
市職員として勤務する公務員のAさんは、自動車を運転中に、目前まで歩行者に気付かず衝突してしまい、歩行者に怪我を負わせてしまいました。
逮捕はされませんでしたが、Aさんは過失運転致傷の容疑で在宅捜査中です。
Aさんに前科前歴はありません。
【過失運転致傷罪とは】
「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」第5条では、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。」とされています。
起こしてしまった交通事故により、被害者が死亡ではなく傷害を負う結果となった場合は、過失運転致傷罪となります。
過失運転致傷罪で起訴され有罪判決となった場合、過失態様、被害者が負った傷害の程度、前科前歴の有無等により刑の重さが決まり、罰金刑(不注意で人身事故を起こしてしまったことに争いがない場合は略式罰金)か禁錮刑(執行猶予が付く可能性は大いにあり)となることが多いです。
【弁護活動】
以下では、人身事故のそれぞれの弁護活動について説明します。
①取り調べへの対応
Aさんは逮捕はされなかったとはいえ、在宅捜査という形で今後警察官、検察官の取調べを受けていくことになります。
過失態様等、事故に関することを詳細に聴取されることになり、最終的な刑事処分への影響もあるので、取調べ対応について弁護士が継続的にアドバイスをすることが大切です。
②被害者との示談
任意保険に入っていていて保険金で賠償をする場合、保険会社の担当者が示談交渉をすることとなりますが、多くの場合は専ら賠償金額に関する示談交渉となるうえ、保険会社の規定に基づいた金額になりますので、被害者の方が刑事処分を求めるか否かという話や保険金では賄えない損害の賠償にまで踏み込んだお話については、弁護士に委任することをおすすめします。
賠償は保険会社に任せることになるとしても、弁護士から被害者の方へ謝罪と賠償に関するお話をさせていただき、保険による賠償金とは別で謝罪金・見舞金のお支払いを申出るなど丁寧に対応をすることで、被害者の方からお許しをいただければ、刑事処分が軽減されることがあります。
被害者の方が重傷でなければ、被害者対応次第で不起訴となることもあり得ます。
③過失を争う
Aさんには何ら不注意がなく、相手が全く予想もしない形で車道に出てきた場合、Aさんには過失がないということになります。周囲の防犯カメラの映像などの客観証拠のほか、被害者の病気や普段の行動についての関係者の供述、何よりAさんの運転についての供述が重要となります。①で述べた取り調べへの対応において、Aさん自身に過失があると受け取られるような不用意な供述をしないことが大切です。
④軽い処罰を目指す
犯罪が成立するとして起訴されてしまうとしても、なるべく軽い処罰にとどめることを目指す必要があります。とくに公務員のAさんの場合、後述のように失職や懲戒処分が問題となるため、罰金刑などの軽い刑罰にとどめることが重要になります。
【刑罰以外の処分等】
公務員の方は、起訴されると、休職をさせられることがあります(地方公務員法第28条第2項第2号、国家公務員法第79条第2号)。
そして起訴され、有罪判決で禁錮以上の刑となれば、執行猶予が付いたとしても、失職することになります(地方公務員法第28条第4項・第16条第1号、国家公務員法第76条・第38条第1号)。
事例の場合、過失が重く、傷害も甚大で、示談不成立の場合、禁錮刑や懲役刑の有罪判決を下される可能性があり、そのような場合失職となります。
ただし、Aさんは市役所の職員で地方公務員であり、地方公務員の場合は、条例により当然に失職とならないようにすることができます(地方公務員法第28条第4項)。自治体により要件が異なりますが、通勤中の交通事故や執行猶予付きの禁錮にとどまるなどの場合が多いです。条例の定める要件に該当すれば、失職せずに済む可能性があります。
また、公務員の方が犯罪にあたる行為をすると、刑事罰とは別に懲戒処分を受けることにもなります。
懲戒処分は、重い順に、免職、停職、減給、戒告と種類があります。
飲酒運転や交通事故を起こしたときの措置義務を果たしていなかった場合、処分が重くなります。それ以外の交通事故では、被害の程度、過失の程度、示談の有無などを踏まえて処分がなされます。
公務員のかかわる性犯罪についてはこちらの記事もご覧ください
【おわりに】
人身事故は、場合によっては刑罰だけでなく失職する可能性もあります。
こういったリスクを回避・軽減するためには、弁護士による適切なアドバイスや活動が必要です。
できるだけ早めに弁護士に相談することをおすすめします。
公務員の官金着服事件-警察官が証拠品の現金を盗んだ事件を基に詳しく解説

【事案】
岡山南署で昨秋、事件の証拠品として保管していた多額の現金の紛失が発覚した事件で、岡山県警は9日、署内の保管庫から現金20万円を盗んだなどとして、窃盗、業務上横領などの疑いで同署巡査長の男(31)を逮捕した。
県警によると、巡査長は「金はパチンコやスロットに使った」と容疑を認めている。保管庫からは約320万円が紛失しており、残る約300万円についても関連を調べる。
逮捕容疑は2023年7月21日午前6時半ごろ、岡山南署内の保管庫から20万円を盗んだほか、同5月、当時入居していた警察官舎の管理人として官舎名義の口座から2回で計7万5千円を引き出し着服するなどした疑い。
昨年10月下旬、岡山南署員らが証拠品を点検した際、現金の紛失に気が付いた。首席監察官は「警察官として言語道断の行為で深くおわび申し上げる。全容解明を図り、厳正に対処したい」とのコメントを出した。
山陽新聞dijital(1月9日火曜日13:30配信)
https://news.yahoo.co.jp/articles/4982b274fa7b834635ab4d0e71d9b63dd6931909
(氏名など個人を特定できる情報は変更しています)
【事案】は警察官が証拠品として保管していた現金を盗んだり、警察官舎の口座から現金を引き出して着服したという疑いで逮捕された事件です。公金を奪った点では同じですが、それぞれ異なる犯罪が成立すると考えられます。
公金着服において成立する犯罪
業務上横領
自己の占有する他人の物を横領した場合横領罪(単純横領罪)が成立し、5年以下の懲役に処されます(刑法第252条第1項)。これが業務上自己の占有する他人の物の場合、業務上横領罪は10年以下の懲役(刑法第253条)に処されます。
「占有」とは、事実上の占有だけでなく、法律上の占有も含まれます。預金なども対象になり得ますが、預金通帳やキャッシュカード等を事務的に預かっているだけでは預金を占有しているとはいえません。【事案】の警察官は警察官舎の管理人なので預金通帳なども自ら管理していると考えられ、「占有」しているといえるでしょう。
「業務」とは、人がその社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務です。公務員がその仕事として行うものであれば「業務上」占有すると判断されるでしょうから、公務員がその業務に関係する物を横領した場合は、多くは業務上横領罪に当たるでしょう。なお、業務上占有できる物を占有していたとしても、業務とは無関係に占有した場合は、業務上占有しているとはいえません。【事案】の警察官は、官舎の口座の金銭を着服した事件については、警察官者の管理人として口座を管理していたと考えられるため、業務上占有していたと考えられます。
「横領」とは、不法領得の意思を実現する一切の行為をいいます。この「不法領得の意思」とは、「他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思」をいうとされています。金銭の着服は横領の典型的な行為です。着服の他に「横領」に該当する行為の態様は、毀棄・隠匿のほか、売却や貸与、譲渡担保や抵当権などの担保権の設定、質入れなど多彩な行為が考えられます。
窃盗
他人の財物を窃取した者は、10年以下の懲役又は10年以下の懲役に処されます(刑法第235条)。
自身に先述の「占有」がない現金などを持ち去れば、この窃盗罪が成立します。【事案】では被疑者は巡査長で警察署の保管庫の管理者などではなく「占有」がないといえ、ここから現金を持ち去れば窃盗となります。
懲戒処分
各都道府県の警察官は地方公務員であり、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合などは、懲戒処分を受けることになります(地方公務員法第29条第1項)。都道府県警察の警察官は警視総監や道府県警察本部長が任命権者となりますので、警視総監や道府県警察本部長が懲戒処分を行います(地方公務員法第6条第1項)。各都道府県が定める懲戒処分に関する条例や規則、指針等に基づいて処分が下されます。
国家公務員についてですが、人事院は「懲戒処分の指針について」にて、懲戒処分の基準を定めています。「第2 標準例」の「2 公金官物取扱い関係」において、「(1)横領 公金又は官物を横領した職員は、免職とする。」、「(2)窃取 公金又は官物を窃取した職員は、免職とする。」と、非常に重い処分が定められています。地方公務員である警察官もこれと同様に処分されるものと考えられます。
参考:懲戒処分の指針について
https://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/12_choukai/1202000_H12shokushoku68.html
こちらの記事もご参照ください
まとめ
このように、公金や官物を横領したり窃取した場合は、非常に重い処分を下されることになります。
公金についてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
自衛官の刑事事件-自衛官が暴行事件を起こしてしまったケースを基に弁護活動や懲戒処分について解説

【事例(フィクション)】
陸上自衛隊の駐屯地で自衛官として勤務するAさんは、居酒屋で同僚とお酒を飲んでいたところ、隣の席のお客さんとトラブルになり、口論の末、そのお客さんの肩をこぶしで殴ってしまいました。
そのお客さんに怪我はありませんでしたが、Aさんは暴行の容疑で、現行犯逮捕されました。
Aさんに前科前歴はありません。
【被疑者の方が自衛官の場合のリスク】
自衛官は、防衛省の特別機関である自衛隊の任務を行う防衛省の職員で、国家公務員となります。
自衛官の方が刑事事件の被疑者となった場合、刑事手続き上の逮捕・勾留や刑事罰のリスクだけでなく、国家公務員法上の懲戒処分や、失職等のリスクにもさらされることとなってしまいます。
以下、弁護活動も含め、順に説明していきます。
【暴行の刑事罰】
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」とされています(刑法208条)。
その他の事情にもよるので一概には言えませんが、Aさんのようなケースでかつ初犯であれば、罰金刑となることが多いです。
【弁護活動】
①まずは弁護士が接見といって、留置場に身体拘束されているAさんとの面会をして、事実確認や取調等の状況確認をし、取調べ対応等のアドバイスをすることが、今後の刑事処分のため重要な弁護活動です。
②Aさんは逮捕されましたが、この後勾留が決定してしまうと、10日間、さらに延長されると最長で20日間の身体拘束となります。
これに対しては、弁護士において、罪証隠滅や逃亡の可能性がないことを主張・疎明し、勾留の阻止を目指す活動(勾留の決定後であれば準抗告という勾留決定の取消しを求める不服申立て)をすることが考えられます。
③Aさんの場合、被害者の方に暴行をしてしまったことは事実なので、弁護士による示談交渉が非常に重要です。
交渉の結果、被害者の方に示談を受けていただければ、不起訴(起訴猶予)となり前科を回避できる可能性が高いです。
【刑事罰以外の処分等】
国家公務員である自衛官の方は、起訴され、有罪判決で禁錮以上の刑となれば、執行猶予が付いたとしても、失職することになります(国家公務員法76条・38条1号)。
事例の場合、Aさんに前科前歴はなく、有罪判決であっても罰金刑の可能性が高く、この規定による失職の可能性は低そうです。
もっとも、国家公務員の方が犯罪にあたる行為をすると、刑事罰とは別に懲戒処分を受けることにもなります。
懲戒処分は、重い順に、免職、停職、減給、戒告と種類があります。
人事院が公表している懲戒処分の指針によると
「具体的な処分量定の決定に当たっては、
① 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか
② 故意又は過失の度合いはどの程度であったか
③ 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか
④ 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか
⑤ 過去に非違行為を行っているか
等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものとする。」
としつつ、標準例では「暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったときは、減給又は戒告とする。」とされています。
Aさんの場合、標準例では減給又は戒告となりそうですが、同指針においては、総合考慮の上で、標準例より重い処分をする場合も軽い処分をする場合もあり得るとされています。
例えば「非違行為後の対応」といった、弁護活動における示談交渉と絡む考慮要素もありますので、リスク軽減のため、弁護士に相談することをおすすめします。
参考
こちらの記事もご覧ください
公務員の懲戒処分
【おわりに】
暴行の容疑をかけられた自衛官の方は、身体拘束、刑事罰、懲戒処分等のリスクにさらされますが、こういったリスクを回避・軽減するためには、弁護士による適切なアドバイスや活動が必要ですので、できるだけ早めに弁護士に相談することをおすすめします。
公務員の懲戒処分の流れ-公務員が罪を犯した場合の懲戒処分の内容や手続きの流れについて解説

刑罰が定められている法令に違反すると、法令に定められた刑罰を科されます。一方で、公務員については、非違行為をしたとして、所属官庁から懲戒処分を下される可能性があります。ここでは、公務員の懲戒処分について解説します。
懲戒処分の根拠
公務員の懲戒について、国家公務員は国家公務員法第82条以下に、地方公務員は地方公務員法第27条以下に定められています。
国家公務員法・地方公務員法とも、懲戒事由について定めています。いずれも、①同法やこれに関係する命令・条例などに違反した場合、②職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合、③全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合、を懲戒事由としています(国家公務員法第82条第1項、地方公務員法第29条第1項)。
犯罪を犯した場合は、③全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合に該当するでしょう。
なお、国家公務員については、特別職国家公務員となるために退職出向し、再び国家公務員として採用された場合、退職出向前の非違行為に対し懲戒処分をすることが可能となっています(国家公務員法第82条第2項)。地方公務員も同様に、特別職地方公務員となるために退職出向し、再び地方公務員として採用された場合、退職出向前の非違行為に対し懲戒処分をすることが可能となっています(地方公務員法第29条第2項)。また、地方公務員が定年前再任用短時間勤務職員として採用された場合、退職前及び採用中の非違行為に対し懲戒処分をすることが可能になっています(地方公務員法第29条第3項)。
懲戒手続を行う者
国家公務員の場合、懲戒処分は任命権者が行いますが、懲戒手続は人事院が行います(国家公務員法第84条第1項・第2項)。
地方公務員の場合は、条例に定められた機関が懲戒手続を行います(地方公務員法第29条第4項)。
刑事手続との関係
公務員の場合、起訴されると、強制的に休職させられることがあります(地方公務員法第28条第2項第2号、国家公務員法第79条第2号)。休職中は仕事ができませんし、給与は支給されません(国家公務員法第80条第4項参照)。
国家公務員法では、刑事裁判が継続中の事件であっても懲戒手続を進めることができる旨定められています(国家公務員法第85条)。重大な事件で本人も認めているような事件では、判決が出る前に懲戒手続がすすめられ、懲戒処分が下されることがあります。
裁判の結果、有罪の判決を言い渡され、禁錮以上の刑に処されると、失職してしまいます(地方公務員法第28条第4項・第16条第1号、国家公務員法第条第76条・第38条第1号)。こちらは法律の規定による当然失職で、懲戒処分ではありません。
ただし、地方公務員の場合は、「条例に特別の定めがある場合」は、失職とならないことがあります。たとえば、東京都の「職員の分限に関する条例」では、「禁錮の刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状により、当該職員がその職を失わないものとすることができる。」と定められています(同条例第8条第1項)。
懲戒処分の種類
懲戒処分には、戒告、減給、停職、免職があります(地方公務員法第29条第1項、国家公務員法第82条第1項)。
①免職・・・公務員の身分を失わせる処分です。
②停職・・・国家公務員の場合、停職の期間は1年以内です(国家公務員法第83条第1項)。停職中は引き続き職員としての身分を有しますが、職務には従事せず、基本的に給与は受け取れません(国家公務員法第83条第2項)。
③減給・・・国家公務員の場合、1年以下の期間で、俸給の月額の5分の1以下に相当する額を給与から減らします。
④戒告・・・戒告は、その責任を確認し、将来を戒める処分です。
非違行為が重いほど、処分は重くなります。特に、公務中や公金・官物の取り扱いに関係する非違行為はより重い処分を下されます。例えば、国家公務員の場合、公金や官物を横領した場合は、免職とするとされています。
人事院は、「懲戒処分の指針について」にて懲戒処分の指針を公表しています。
地方公共団体においても、懲戒処分の指針を定めています。
参考:東京都知事部局職員の懲戒処分についての「懲戒処分の指針」
懲戒処分以外の指導
公務員が不祥事を起こしたときに、「訓告」や「厳重注意」を受けたと言われることがあります。これらは、上級監督者から部下職員に対する指導、監督上の措置として行われるもので、懲戒処分ではありません。
懲戒処分の問題
非違行為の中でも、公金官物の取り扱いに関して犯罪を行うと免職となることが多いです。重大な犯罪を行っても免職処分を下される可能性が高いです。
また、飲酒運転をした場合も免職となることが多いです。その他の交通事故でも、措置義務違反(道路交通法第117条第1項・第72条第1項前段)があればさらに重い処分となるでしょう。
また、地方公務員の場合、痴漢事件や盗撮事件などでも免職となりうるなど、国家公務員より重い処分となる傾向にあります。
公務員の懲戒処分についてはこちらもご覧ください
まとめ
以上のように、公務員が犯罪を犯すと刑罰だけでなく懲戒処分を科されます。失職や免職となると、退職金が支給されないことになります。そのため、免職や失職を避けることが重要となります。
公務員の方で懲戒処分についてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
消防士の刑事事件-消防士が痴漢事件を起こしたケースを基に、弁護活動や懲戒処分について解説

【事例(フィクション)】
消防署に消防士として勤務するAさんは、電車内で被害者のお尻を触ったという迷惑防止条例違反(痴漢)の容疑で、警察に逮捕されました。
Aさんに前科前歴はありません。
【被疑者の方が消防士の場合のリスク】
消防署に勤務する消防士は、地方公務員となります。
消防士の方が刑事事件の被疑者となった場合、刑事手続き上の逮捕・勾留や刑事罰のリスクだけでなく、地方公務員法上の懲戒処分や、失職等のリスクにもさらされることとなってしまいます。
以下、弁護活動も含め、順に説明していきます。
【迷惑防止条例違反(痴漢)の刑事罰】
いわゆる痴漢行為は、それぞれの都道府県において定められている迷惑防止条例違反にあたることが多く、罰金刑又は懲役刑に処すると定められています。
迷惑防止条例違反の事案は、初犯であれば罰金刑となることが多いです。
なお、痴漢行為は、行為の状況や程度次第では、より重い不同意わいせつ罪(刑法176条1項、6月以上10年以下の懲役刑(拘禁刑))にあたることもあります。
【弁護活動】
①まずは弁護士が接見といって、留置場に身体拘束されているAさんとの面会をして、事実確認や取調等の状況確認をし、取調べ対応等のアドバイスをすることが、今後の刑事処分のため重要な弁護活動です。
②Aさんは逮捕されましたが、この後勾留が決定してしまうと、10日間、さらに延長されると最長で20日間の身体拘束となります。
これに対しては、弁護士において、罪証隠滅や逃亡の可能性がないことを主張・疎明し、勾留の阻止を目指す活動(勾留の決定後であれば準抗告という勾留決定の取消しを求める不服申立て)をすることが考えられます。
③Aさんが容疑のとおり痴漢行為をしたことで間違いないのであれば、弁護士による示談交渉が非常に重要です。
交渉の結果、被害者の方に示談を受けていただければ、不起訴(起訴猶予)となり前科を回避できる可能性があります。
④Aさんが痴漢行為をしたとしても、重い不同意わいせつ罪ではなく、迷惑防止条例違反を適用するよう主張することが考えられます。
⑤Aさんは容疑のとおりの痴漢行為をしていない、いわゆる冤罪の場合は、弁護士が取調べ対応をしっかりサポートするなどしながら、まずは不起訴(嫌疑不十分)を目指します。
⑥冤罪であるにもかかわらず起訴されてしまった場合、Aさんは、有罪判決となれば罰金刑又は懲役刑となってしまいます。
弁護士としては、無罪判決の獲得のため、開示された証拠を精査して検察官の立証の穴を突くとともに、無罪であることを示す証拠があるか検討していきます。
【刑事罰以外の処分等】
地方公務員の方は、起訴されると、休職をさせられることがあります(地方公務員法28条2項2号)。
そして起訴され、有罪判決で禁錮以上の刑となれば、執行猶予が付いたとしても、失職することになります(地方公務員法28条4項・16条1号)。
事例の場合、Aさんに前科前歴はなく、有罪判決であっても罰金刑の可能性が高く、この規定による失職の可能性は低そうです。なお、不同意わいせつ罪の場合、罰金刑がありませんので、なおのこと起訴されないようにする必要があります。
もっとも、地方公務員の方が犯罪にあたる行為をすると、刑事罰とは別に懲戒処分を受けることにもなります。
懲戒処分は、重い順に、免職、停職、減給、戒告と種類があります。
東京都が公表している懲戒処分の指針によると
「具体的な量定の決定に当たっては、
① 非違行為の態様、被害の大きさ及び司法の動向など社会的重大性の程度
② 非違行為を行った職員の職責、過失の大きさ及び職務への影響など信用失墜の度合い
③ 日常の勤務態度及び常習性など非違行為を行った職員固有の事情等のほか、適宜、非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものとする。
個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる量定にかかわらず免職等の処分をすることもあり得る。」
としつつ、標準例では「公共の乗物等において痴漢行為をした職員は、免職又は停職とする。」とされています。
Aさんの場合、痴漢行為が事実であれば免職のリスクがあることとなりますが、例えば「非違行為後の対応」といった、弁護活動における示談交渉と絡む考慮要素もありますので、リスク軽減のため、弁護士に相談することをおすすめします。
参考:懲戒処分の指針
公務員の性犯罪や懲戒処分については、こちらもご覧ください。
【おわりに】
迷惑防止条例違反(痴漢)の疑いをかけられた消防士の方は、身体拘束、刑事罰、懲戒処分等のリスクにさらされますが、こういったリスクを回避・軽減するためには、弁護士による適切なアドバイスや活動が必要です。
実際に痴漢行為をしてしまった方も、冤罪の方も、できるだけ早めに弁護士に相談することをおすすめします。
公務員とアルコールに関わる犯罪

公務員の方々は、安定した地位で真面目に仕事をして生活をしていることが多いので、事件を起こすことについても注意をしている人が多いです。
そのような公務員の方々ですが、アルコールで失敗して犯罪を行ってしまうことがあります。
気が付いた時には後悔の感情でいっぱいで、弁護士に相談・依頼するケースが少なくありません。
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が、アルコールで失敗して犯罪を行ってしまったケースについて解説いたします。
飲酒運転
公務員の方々であれば、普段から代行を頼んだり徒歩で移動したりして、気を付けている人が多いです。
しかし、お酒が入ることで気が大きくなり、飲酒運転をしてしまうケースがあります。
この程度なら大丈夫だ、短い距離だから大丈夫だ、自分なら大丈夫だ、急ぎの用があるから仕方がない、などと考えて運転してしまうのです。
道路交通法で、酒気を帯びて車両等を運転することが禁止されております。
身体に保有するアルコールの程度が、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上であれば、酒気帯び運転として3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります(道路交通法第117条の2の2第1項第3号・道路交通法施行令第44条の3)。
さらに、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態であれば、酒酔い運転として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(道路交通法第117条の2第1項第1号・第65条第1項)。
飲酒運転により、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、過失運転致死傷罪として7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となります(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)。さらに、アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で自動車を走行させて人を死傷させたと判断された場合は、危険運転致死傷罪としてさらに重い犯罪となり、負傷させた場合は15年以下の懲役、死亡させた場合は1年以上の有期懲役となります(同法第2条第1号)。
人身事故を起こし、救護措置や警察への連絡をせずに逃げたら、更に轢き逃げとなり、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(道路交通法第117条第2項)。
性犯罪
アルコールで酔って、性犯罪を行ってしまうケースも多いです。
普段のストレスを解消するため、飲食店で過剰な飲酒をしてしまい、帰りに性犯罪を行ってしまいます。
酔いが覚めたら自分のした事を覚えていないが逮捕されていた、という状況が珍しくありません。
酔っぱらって、外で下半身裸で歩き回る人もいます。
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となります(刑法第174条)。
酔っぱらって、いわゆる痴漢行為をしてしまう人もいます。
公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、衣服等の上から、又は直接身体に触れる行為をしたら、迷惑行為防止条例違反となります。東京都の場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
更に強い態様のわいせつ行為をしたら、不同意わいせつ罪が成立します。
逆に、他人にお酒を飲ませて、断るのが困難な状態にしてわいせつ行為をしても、不同意わいせつ罪が成立します。
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の懲役刑(拘禁刑)となります(刑法第176条第1項)。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
また、不同意わいせつ罪の各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものである性交等をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、不同意性交等罪として5年以上の有期懲役刑(拘禁刑)となります(刑法第177条第1項)。
その他の犯罪
住居侵入
酔って気が大きくなり、他人の家に侵入するケースもあります。
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、住居侵入罪として3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となります(刑法第130条)。
窃盗
酔った勢いで、お店や他人の家で物を持って行ってしまうケースもあります。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります(刑法第235条)。
暴行・傷害
酔って人に対して因縁をつけ、暴力を振るうこともあります。
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、暴行罪として2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となります(刑法第208条)。
人の身体を傷害した者は、傷害罪として15年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります(刑法第204条)。
器物損壊
酔ってお店などの物を壊してしまうこともあります。
他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料となります(刑法第261条)。
まとめ
公務員がアルコールで失敗して犯罪を行ってしまったら、失職や懲戒処分となる可能性があります。
アルコールに関わる犯罪でお悩みの方はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
今後の対応について、丁寧にご説明いたします。
こちらの記事もご覧ください。
公務員のパワハラと犯罪-公務員がパワハラを起こした場合の懲戒処分や刑罰をはじめとしたその他の処分について解説

自衛隊内でのパワハラなど、公務員のハラスメントが問題となっています。このようなパワハラは懲戒処分の対象になりますし、悪質なものは刑事事件となってしまいます。ここでは、公務員がハラスメントをした場合どうなるかについて解説します。
パワハラとは
パワーハラスメント(パワハラ)とは、①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業関係が害されるものであり、①~③までの要素のすべてを満たすものをいいます。①優越的な関係とは、上司や部下という関係が一般的ですが、部下であっても代替できない資格・技能を有していたり、多数の部下が共同して業務に支障が出るようにする場合も、優越的な関係を背景としたといえます。②については、厳しい叱責であっても、客観的に見て、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しません。これを越えた、業務とは無関係な話や、殊更に他の職員のいる前でさらしものにしたり、人格攻撃に至れば、業務上必要かつ相当な範囲を超えたとされます。③については、①や②に該当する言動が行われれば、その対象となった者の心身に不調をきたしますし、職場内も対象になった者に不当な対応をする雰囲気になったりするため、該当することになるでしょう。
懲戒処分
公務員がその職務に関してパワハラをすると、非違行為をしたとして、重い懲戒処分を受けることになります。
国家公務員については、「人事院ハラスメント防止リーフレット」や「義務違反防止ハンドブック」に、ハラスメントの防止や懲戒処分の指針について記載されています。また、人事院の懲戒処分の指針にも、パワハラなどをした場合の懲戒処分について定められています。
人事院の懲戒処分の指針によると、「1 一般服務関係」において、「(15)パワー・ハラスメント」の「ア 著しい精神的又は身体的な苦痛を与えたもの」は停職・減給・戒告の対象となります。「イ 指導、注意等を受けたにもかかわらず、繰り返したもの」は戒告では済まされず、停職又は減給とより重くなります。「ウ 強度の心的ストレスの重責による精神疾患に罹患させたもの」は免職・停職・減給の対象となり、もっとも重い懲戒免職もありえます。これらの事案について処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断するものとしています。
参考
人事院ハラスメント防止リーフレット
「義務違反防止ハンドブック」
懲戒処分の指針について
犯罪・刑事責任
パワハラに含まれる行為であっても、その態様や状況によって様々なものがあり、行政庁内の懲戒処分にとどまらず、民事責任、さらには刑事責任を負う行為もあります。
相手に暴行したり怪我を負わせた場合、暴行罪(刑法第208条)や傷害罪(刑法第204条)に問われる可能性があります。殴るなどの有形力の行使によって怪我をさせただけでなく、強いストレスを与えて相手を精神疾患に罹患させた場合も、傷害罪になりえます。個室に数名しかいない状況で叱責するようなものではなく、大勢の人がいる場所で侮辱したり人格を否定するような罵倒をすれば、侮辱罪(刑法第231条)や名誉毀損罪(刑法第230条)が成立する可能性があります。
また、懲戒処分において、「これらの事案について処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断する」と書きましたが、刑事事件として処理される場合、さらに懲戒処分も重くなる可能性があります。上述の人事院の懲戒処分の指針では「3 公務外非行関係」で「(3)傷害 人の身体を傷害した職員は、停職又は減給とする。」と定めていますが、パワハラで人を傷害させたといえるときは、これと同等以上の処分を受けることにもなります。
なお、国家公務員法では、刑事裁判が継続中の事件であっても懲戒手続を進めることができる旨定められています(国家公務員法第85条)が、起訴される前に懲戒処分を下されることもあります。
公務員のパワハラについては、次の記事もご覧ください。
まとめ
このように、公務員がパワハラを起こした場合、懲戒処分や刑罰など多くの不利益が科される可能性があります。ご自身の言動がパワハラに当たるかお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
公務員の不同意わいせつ事件と弁護活動-公務員が不同意わいせつ事件を起こした場合の弁護活動について解説

【事例(フィクション)】
市職員として勤務する公務員のAさんは、路上で被害者の胸をいきなり揉むという不同意わいせつ行為をしたという容疑で、警察に逮捕されました。
Aさんに前科前歴はありません。
【不同意わいせつ罪とは】
刑法176条1項では、「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑(現在は懲役刑として扱われています。)に処する。」とされており、暴行脅迫等の事由が8つ定められています。
Aさんの容疑の内容である、胸をいきなり揉むという行為は、その行為自体が「暴行」(同項1号)とされることがありますし、また、「同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと」(同項5号)にも該当し得ます。
【弁護活動】
①まずは弁護士が接見といって、留置場に身体拘束されているAさんとの面会をして、事実確認や取調等の状況確認をし、取調べ対応等のアドバイスをすることが、今後の刑事処分のため重要な弁護活動です。
②Aさんは逮捕されましたが、この後勾留が決定してしまうと、10日間、さらに延長されると最長で20日間の身体拘束となります。
これに対しては、弁護士において、罪証隠滅や逃亡の可能性がないことを主張・疎明し、勾留の阻止を目指す活動(勾留の決定後であれば準抗告という勾留決定の取消しを求める不服申立て)をすることが考えられます。
③Aさんが容疑のとおり不同意わいせつ行為をしたことで間違いないのであれば、弁護士による示談交渉が非常に重要です。
交渉の結果、被害者の方に示談を受けていただければ、不起訴(起訴猶予)となり前科を回避できる可能性があります。
④Aさんは容疑のとおりの不同意わいせつ行為をしていない、いわゆる冤罪の場合は、弁護士が取調べ対応をしっかりサポートするなどしながら、まずは不起訴(嫌疑不十分)を目指します。
⑤起訴されてしまった場合、Aさんは、有罪判決となれば拘禁刑(懲役刑)となってしまいます。
Aさんが容疑を認めている場合は、弁護士は、拘禁刑(懲役刑)に執行猶予を付けて、実刑を回避することを目指し、情状に関する立証活動をします。
Aさんが冤罪の場合は、弁護士は、無罪判決の獲得のため、開示された証拠を精査して検察官の立証の穴を突くとともに、無罪であることを示す証拠があるか検討していきます。
【刑罰以外の処分等】
公務員の方は、起訴されると、休職をさせられることがあります(地方公務員法28条2項2号、国家公務員法79条2号)。
そして起訴され、有罪判決で禁錮以上の刑となれば、執行猶予が付いたとしても、失職することになります(地方公務員法28条4項・16条1号、国家公務員法76条・38条1号)。
事例の場合、不同意わいせつ罪には懲役刑という禁錮以上の刑(拘禁刑に統合されることが予定されています)しかないので、有罪判決なら失職となります。
また、公務員の方が犯罪にあたる行為をすると、刑事罰とは別に懲戒処分を受けることにもなります。
懲戒処分は、重い順に、免職、停職、減給、戒告と種類があります。
事例のような不同意わいせつ罪にあたる行為をしてしまった場合は、懲戒免職となってしまう可能性が十分考えられます。
もっとも、冤罪の場合は、嫌疑不十分の不起訴や無罪判決を得られれば、懲戒免職を避けられる可能性があります(判断者が異なるので一概には言えませんが。)。
公務員のかかわる性犯罪についてはこちらの記事もご覧ください
【おわりに】
不同意わいせつ罪は、起訴されれば罰金では済まない、決して軽くない事件ですから、同罪の疑いをかけられた被疑者・被告人の方は、身体拘束、刑事罰、懲戒処分等のリスクは非常に大きいといえます。
こういったリスクを回避・軽減するためには、弁護士による適切なアドバイスや活動が必要です。
実際に不同意わいせつ行為をしてしまった方も、冤罪の方も、できるだけ早めに弁護士に相談することをおすすめします。
公務員犯罪と懲戒-公務員が犯罪を起こしてしまった場合に受ける懲戒処分について解説

公務員が犯罪などを行ってしまった場合、懲戒処分を受ける可能性があります。
公務員への懲戒処分は、犯罪などを行った公務員に対して、任命権者が公務員関係における秩序を維持する目的のため、公務員に科する処分です。
懲戒事由
公務員の懲戒事由は、主に以下の3つです(国家公務員法第82条第1項・地方公務員法第29条第1項参照)。
・職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
・全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
公務員犯罪との関係では、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」が問題となってきます。
懲戒処分の中身
懲戒処分は、免職、停職、減給、戒告があります。
免職は、職員の身分を剥奪し、公務員関係から排除する処分です。
失職することになります。
停職は、一定の期間、職員としての身分を保有させたまま職務に従事させない処分です。
その間の給与は支払われません。
減給は、一定の額を給与から減額する処分です。
経済的な不利益を受けることになります。
戒告は、その責任を確認し、将来を戒める処分です。
注意されることになり、懲戒処分を受けた事実が残ることになります。
懲戒処分を受けると、期末・勤勉手当、退職手当、昇任、昇格、昇給などにも影響します。
懲戒処分にはあたらなくても、職員の自覚と反省を促すための実務上の措置として、訓告、厳重注意、口頭注意、等が行われることがあります。
懲戒処分は、公表されることがあります。
懲戒処分の手続は、懲戒処分書と処分説明書を併せて職員に交付することになります。
懲戒処分の効力は、職員に懲戒処分書を交付したときに発生します。
具体的な懲戒処分の内容の決定
職員に懲戒事由があるときに、懲戒処分を行うか、いかなる懲戒処分を選ぶか、については任命権者・懲戒権者の裁量に任されています。
人事院では、懲戒処分がより一層厳正に行われるよう、任命権者が懲戒処分に付すべきと判断した事案について、処分量定を決定するに当たっての参考に供することを目的として、懲戒処分の指針が示されております。
具体的な処分量定の決定に当たっては、
① 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか
② 故意又は過失の度合いはどの程度であったか
③ 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか
④ 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか
⑤ 過去に非違行為を行っているか
等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものとされます。
公務員犯罪と懲戒については、こちらの記事もご覧ください。
おわりに
公務員が犯罪を行ってしまったらすぐにご相談ください
公務員が犯罪を行ってしまった場合、懲戒処分などによる悪影響は他の一般の人よりも大きいです。
出来るだけ不利益を小さくするために、早期に弁護士に相談しましょう。
捜査・取調べへの対応や、被害者への対応などについて、具体的にどのようにすればいいか、懇切丁寧に説明させていただきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで多くの公務員の方々の相談に対応し、事件を扱ってきました。
中には、事件が発覚してしまったショックで、思考停止に陥り、時間が経過するまま対応を放置するような人もいます。
時間が経てば経つほど状況は不利になっていく可能性が大きいですので、なるべく早い対応が必要になってきます。
ご本人だけの問題ではなく、ご家族にも悪影響が大きくなってしまいますので、なるべく早くご相談ください。
まずはお気軽に無料の面談に申し込んでください。
親身になってご対応させていただきます。
0120-631-881までお電話してください。
24時間365日、受け付けております。
日時を調整させていただいて、早期に面談を実施いたします。
« Older Entries Newer Entries »